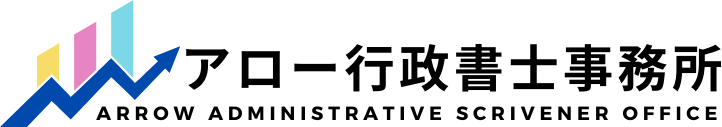酒類販売業免許申請は難易度は比較的高い方に入るかと思います。
お客様の状況によってはすんなり取得できるケースもありますが、特に場所に関する要件がシビアで苦戦する傾向にあると感じています。
このページでは、そんな酒類販売業免許申請の取得方法や難易度、つまづく点について解説していきます。
なお、酒類販売業免許と一口に記載しましたが、取得する免許区分や地域、個々人の置かれている状況によって違いは出てきます。このページでは一般的なよくある例をもとに解説しておりますのでご注意ください。
ご自身での申請が難しそうと感じる場合はアロー行政書士事務所の酒類販売業免許申請代行・サポートサービスの利用もご検討ください。
酒類販売業免許取得方法とその流れ
はじめに、酒類販売業免許取得までの大まかな流れを把握しておきましょう。
酒類販売業免許といってもさまざまな免許区分があります。
ご自身にどの免許が必要なのか?を理解せずに進めてしまい、後から余計な手間がかかるケースもあるため、最初にしっかり整理をするようにしてください。
そもそも酒類販売業免許の取得が可能な状況なのか?自社の状況(決算要件や代表者の能力・経験、オフィスの契約形態等)含めてしっかりと精査する必要があります。
また必要に応じて酒類販売管理研修の受講等も進めておいてください。
ある程度免許取得要件がクリアできていると判断できた段階で税務署との事前相談を実施します。ここで必要な免許の種類、現在の状況を酒類指導官の方にお伝えすることで、ある程度免許取得の可否は判断できます。
申請に必要となる必要書類が何なのかを把握し、準備をする必要があります。
承諾書の取得などご自身の努力ではどうにもならない部分で苦戦するケースもございます。
この段階にきてようやく酒販免許申請書の作成に着手となります。
完成したら申請書の提出をします。
不備がある場合は補正の通知がきます。また、追加書類の提出が求められる場合もあります。
申請書等に問題がなければ登録免許税等を納め、免許取得となります。
大まかな流れとしては上記のような形となります。
ご相談で意外と多いのが、そもそもどの免許が必要かわからないといったケースです。
そこから相談は可能なので、免許取得でお困りでしたらぜひアロー行政書士事務所の利用もご検討ください。
どの酒類販売業免許の取得が必要なのかを明確にする
酒類販売業免許申請にあたり、どの酒類販売業免許が必要になるのかを明確にし、それに合わせた申請をしていく必要があります。
免許の種類としては、大きく分類すると一般消費者に販売するのに必要となる「酒類小売業免許」、酒類免許業者向けに販売するために必要な「酒類卸売業免許」に大別できますが、どの免許が必要になるかは「どのようなお酒を」「どこから仕入れ」「誰に対して」「どのように売るのか」によって変わってきます。事業内容によっては複数の免許が必要になるケースも多くなっています。ここでは主要な免許の区分について簡単に見ていきたいと思います。なお、各種免許の種類については、酒類販売業免許の種類を解説!のページをご覧ください。
一般酒類小売業免許
もっとも申請の需要が大きいと感じるのは一般酒類小売業免許です。
この免許は1都道府県内にて一般消費者(飲食店含)向けにすべての酒類が販売できる免許です。
店舗を構えて消費者向けにお酒を販売する、飲食店向けに配達でお酒を販売するといった場合に必要な免許となります。
通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上に向けて通信販売による手段で一般消費者へお酒を販売する場合は通信販売酒類小売業免許が必要となります。
通信販売とはECサイト等のネット販売やカタログ販売が該当します。
販売できる酒類の品目に制限があり、輸入酒であれば制限はありませんが、国産酒の販売にあたっては課税移出数量3,000kl未満等の条件があります。
洋酒卸売業免許
ワインやウイスキーなどの洋酒を酒販免許業者等へ卸売する際に必要な免許です。
洋酒の中で指定を受けた品目について卸売ができる免許となります。
輸出入酒類卸売業免許
お酒を輸入して卸売をする、あるいはお酒を輸出する場合に必要な免許です。
輸出入酒類卸売業免許と国税庁の手引きにも記載されているので一見すると1つの免許に見えるのですが、輸出と輸入はそれぞれ別の免許となります。
なお、あくまで卸売をするのに必要な免許なので、輸入酒を一般消費者へ販売するのであれば、先に紹介した一般酒類小売業免許等が必要となります。
一方で輸出してお酒を販売する場合においては、輸出先国の一般消費者への販売であっても輸出酒類卸売業免許が必要となります。
自己商標酒類卸売業免許
自社・自己が開発したオリジナルのお酒を卸売する際に必要な酒類販売業免許です。
すべての品目の酒類が取扱い可能ですが、あくまで自己が開発したもののみとなります。
また、申請にあたっては自己が開発したオリジナルラベルのお酒であることを疎明する資料が求められます。
酒類販売業免許の要件を満たせず取得が難しい場合が多い
酒類販売業免許は申請すれば誰でも取得できるというものではありません。そのため、まずは自社(自分)の状況的に免許取得が可能なのかを確認しましょう。
なお、ここではすべてを細かく見ていくことは難しいため、主要な要件やつまづきやすいポイントに絞ってみていきます。酒類販売業免許申請における要件について細かく把握したい方は以下のページをご覧ください。
決算要件でつまづくケースがある
過去3期の決算において資本等の額の20%を超える赤字を3期連続で出している場合や直近の決算における貸借対照表の繰越損失の額が資本等の額を上回っている場合などは酒類販売業免許が取得できないため、まずは自社の経営状況について確認しましょう。
場所に関する要件を満たせないケースや承諾書の取得ができず申請が難しいケースがある
酒類販売業免許の取得にあたり、原則として飲食店等と同一の場所で免許を取得することができない(あくまで原則であり例外として取得することは可能)など、場所に関する要件は意外と厳しく設定されています。
※飲食店が酒販免許を取得する場合は必要書類や準備するものが多くなるためご注意ください。
また、店頭販売をするケースにおいて、賃貸借契約書上で酒類販売業に関する記載がない場合などは契約書の変更あるいは賃貸人から承諾書等が求められる場合がある他、賃貸人と建物所有者が異なる場合は所有者の承諾書や所有者と賃貸人との契約書の提出が求められるケースもあるでしょう。
この他、自己所有のマンションで酒類販売業免許を取得しようと思う際は管理組合等からの承諾も必要です(事業利用不可のマンションが多いため)。
ネックになるのが小規模の事業者様でレンタルオフィスを検討しているケースや自宅の賃貸マンションでまずは免許を取得しようとお考えのケースにおいて、賃貸人は免許申請しても大丈夫と言っているが、所有者からの承諾書等をもらうことができず、断念するケースというのが結構あります(所有者と賃貸人が異なるケースは結構多いかと思います)。
また、賃貸ではなく購入したマンションというケースにおいては管理組合がNGというケースも多いので、場所が決められず酒類販売業免許申請ができないといったケースは一定数ございます。
税金の滞納・未納やお酒に関する違反等をしていないかどうか
過去に酒類販売業免許の取消処分を受けていたり、国税や地方税の滞納処分を受けていたりする場合は酒類販売業免許の取得が難しい場合があります。
こうした基本的な要件がクリアできているかは確認する必要があります。
仕入先や販売先の確保が難しい場合がある
お酒の販売をするかもしれないからとりあえず酒類販売業免許だけ取得しておこう、といったことはできません。
ある程度仕入先・販売先を少なくとも1つはしっかりと確保し、すぐに酒類販売業が始められる状態になっていないと申請が難しいといえます。
どこから仕入れ、誰に販売するのか、これが定まっていないのにとりあえず免許申請したいという方は結構多くいらっしゃるのでご注意ください。
特に酒類卸売業免許では取引承諾書の提出が必要となるので一定以上の関係性は必要と言えます。
必要な経験値が不足していて免許が取れない場合もある
免許区分により変わってくるところもありますが、酒類販売業免許では経営経験や酒類業界での経験が求められています。
既に会社を経営している場合は経営経験については問題ない場合も多くなっていますが、副業で酒類販売業免許を取得したいというケースや脱サラして初めて事業をするという方の場合は経営経験がクリアできない場合もあります。
税務署から無理ですね、といわれて諦めてしまう方もいらっしゃいます。
ただ、経営者としての実務経験がないと絶対に免許が取れないかというとそんなこともありません。過去の経験を棚卸し、整理する必要はありますが、経営経験がなくても免許の取得は出来るケースがあります。
税務署との事前相談を実施
自社のビジネス・商流を明確にし、どの酒販免許が必要なのか、要件はクリアできていそうかなどの確認ができたら、今度は税務署と事前相談を行うといいでしょう。
事前相談は酒類指導官が設置された税務署となり、申請先とは異なりますのでご注意ください。
また、事前相談にあたっては概要をまとめた資料を作成しておくと相談時はもちろんその後もスムーズになるかと思います。
アロー行政書士事務所では事前相談の代行のみというのも行っておりますので、事前相談でお困りであればサービスのご利用をご検討ください。
必要書類を把握し取得する
税務署との事前相談で酒類販売業免許の取得ができそうなことがわかったら、どのような書類が必要になるのかを把握し、取得してください。
具体的には、申請書や次葉の1~6、納税証明書、登記事項証明書(土地・建物)、定款、契約書等となります。
ご状況や取得する免許により異なり、このページではすべてを解説できませんので、必要書類については以下をご参考ください。
申請書の作成をする
酒類販売業免許申請書は国税庁のサイトからダウンロードすることができます。
申請書の記入自体はそこまで難しいものではありませんが、次葉の1~6まで含め、記入する箇所が多いので、手間はかかるかと思います。
また、酒類販売業免許はその「場所」に対して付与されるので、場所に関しては結構詳細な情報が求められます。
住居表示なのか地番表記なのかなど細かい点で注意が必要です。
管轄の税務署へ提出する
申請書が完成したら販売場の管轄の税務署へ提出します。事前相談をした税務署とは異なる場合が多いかと思いますのでご注意ください。
提出自体はそれほど難しいイベントではなく、本当にただ提出するだけです。
補正や追加資料が発生する場合は税務署から連絡がきます。
なお、現在は2部作製しても副本は用意してくれないため、提出する分だけの作成でOKです。
登録免許税を納める
提出し書類に問題がなければ登録免許税納付等に関する書類が税務署から届きます。
納めたうえで領収書を貼り付けて税務署に提出しましょう。
なお、登録免許税も含めて酒類販売業免許申請にかかる費用について知りたい方は以下のページもご参考ください。
酒類販売業免許の交付を受ける
酒類販売業免許申請の標準処理期間は2カ月となっているので、大きな問題がなければ申請から2カ月程度で免許が取得できるということとなります。
更新はないが免許を取得してそれで終わりではない
酒類販売業免許の交付を受ける際にも注意がありますが、酒類販売業においては日々の取引についてしっかりと帳簿付けを行い、税務署へ申告する義務があります。
また、免許取得後に取り扱う品目等を追加する場合は条件緩和の申請が必要となる場合がある他、その他の項目でも変更があれば届出等の手続きが必要な場合もあります。
酒類販売業免許は更新制ではありませんが、変更や追加が必要な場合は適切な手続きを行う必要があります。
免許要件を満たしているかの確認から税務署との事前相談まで確認が面倒で難しい
どの酒類販売業免許を取得するべきか?要件を満たしているか?などの確認から申請書の作成、必要書類の収集等、申請にあたって必要なことを確認するのは意外と大変です。
酒類販売業免許申請は申請するまでの確認で時間がかかるため、お困りであればぜひ行政書士の活用も視野に入れていただければと思います。
アロー行政書士事務所の酒類販売業免許申請代行・サポートサービスについては詳細ページがありますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。