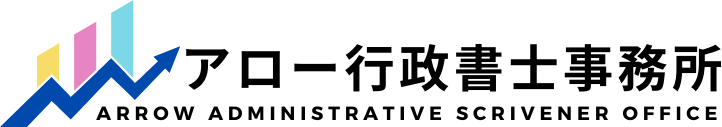ワインバーや居酒屋、レストランと同一の場所で酒類販売業免許を取得したいという要望は増加傾向にあると感じます。
ただ、原則として飲食店等と同一の場所では酒類販売業免許は取得できないこととなっており、基本的に酒販免許は取得できないということになります。
それでは酒類販売業免許の取得を諦めなければならないのかというとそんなことはありません。実際に同一の場所でお酒を販売しているお店を見かけるケースもあるかと思います。あくまで原則不可なだけであり、一定の条件を満たすことで例外的に飲食店も酒類販売業免許は取得可能です。
そこで、このページでは、近年要望の増えている飲食店等が酒類販売業免許を取得するにあたっての条件やポイントについて解説していきます。
なお、アロー行政書士事務所では飲食店での酒類販売業免許申請の支援・代行も行っております。お困りの方はぜひご相談ください。酒販免許申請代行・サポートに関するサービスページはこちらからご覧いただけます。
※コロナ禍では特例で飲食用に仕入れたお酒を小売することも認められましたが、それはあくまで特例中の特例であり、現在はもうその特例はありませんのでご注意ください。
原則として飲食店は酒類販売業免許は取得できないが条件を満たすことで可能となる場合も多い
酒類販売業免許申請の手引きにも記載されていますが、需給調整要件により、原則として飲食店は酒類販売業免許は取得できません。
酒類販売業免許取得の要件として、酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要との記載があります。
ただ、注意書きとして、「国税局長において販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場合には、免許を受けることができます。」とも記載されています。
つまり、原則的にはダメだけど、条件を満たした上で申請をすることで、例外的に免許を取得することが可能になるということです。
感覚的な部分となりますが、実際に取得されるケースは増えているように思います。
酒類販売業者として仕入れたお酒を飲食店用のお酒として提供することはできない
飲食店で酒類販売業免許を取得したいという方の中には、酒販業者としてお酒を仕入れ、その仕入れたお酒を飲食店で提供したいということをおっしゃるケースもあるのですが、それは認められません。
逆も同様です。
相互に転用することはできませんのでご注意ください。
また、酒販業者は年間の仕入れ・販売数量等を報告する必要があるため、しっかりとそれぞれが管理できることが求められることに注意が必要です。
酒類販売業免許を飲食店が取得するなら飲食業と酒類販売業を明確に区分する必要がある
飲食店が酒類販売業免許を取得するにあたっては、通常の要件クリアに加えて、飲食店事業と酒類販売事業を明確に区分することが重要です。
通常の要件はともかくとして、飲食と酒販事業を明確に区分するとはどういうことになるのでしょうか?
飲食用のお酒と酒販用のお酒の仕入を明確に区分する
飲食店で提供するお酒と酒類販売業者として販売するお酒の仕入れについては、明確に区分して管理する必要があります。
ご存知の通り、飲食店としてお酒を仕入れる場合は、酒類小売業者あるいは酒類の製造者からの仕入れになります。一方で、酒類販売業者としてお酒を仕入れる場合は、酒類卸売業者あるいは酒類の製造者からの仕入れとなります。
仕入先は飲食店用と酒類販売用で異なる場合が多いかと思いますが、酒類製造者から直接仕入れていたり、卸売業免許と小売業免許の両方を持つ業者から仕入れていたりする場合は同じということもあります。ただ、小売・卸売で業態が異なるため、同一の仕入先であっても用途別に分けて仕入れを管理することが重要です。
具体的には、発注時点で飲食用か酒類販売用かを明記し、帳簿・伝票上でも分けて記録・管理します。また、在庫管理においても用途別の管理を行い、報告の際にはそれぞれの用途に応じた適切な処理を行う必要があります。
【補足】
酒類販売業者から飲食店へのお酒の販売は、酒販免許の制度上では、卸売ではなく小売となります。
現場では飲食店へ「卸す」と表現するケースが多いかもしれませんが、制度上は小売となります。
なので、飲食店がお酒を仕入れる場合は酒類小売業免許を持っている業者から仕入れることとなります。
なお、酒類販売業者への販売は卸売りになるので、酒販業者として仕入れを行う場合は酒類卸売業免許を持っている業者から仕入れることとなります。
お酒の保管場所も飲食用と酒販用で区分する必要がある
先ほど説明した在庫管理の区分と同様に、物理的な保管場所についても分けて管理しなければなりません。
原則的には、飲食用の棚と酒販用の棚を完全に分ける、または冷蔵庫を用途別に用意して使い分けるといった対応が求められます。ただし、店舗の物理的な制約がある場合には、同一の棚内であっても明確に区画を設けることで区分管理が認められるケースもないことはないです。
この点については、各店舗の構造や設備状況、販売する酒類によって対応方法が変わってくるため、現実的な制約を考慮しながら、税務当局から見ても「確実に区分されている」と判断されるような管理体制を構築することが重要です。
お酒の販売場所と飲食場所が区分されている
お酒の販売場所と飲食場所についても明確に区分する必要があります。
飲食スペースと酒類販売スペースがそれぞれどこに位置するのかを明確にし、その区分を適切に示さなければなりません。これは、同一店舗内で飲食業と酒類販売業の両方を営む場合の重要な要件となります。
以前は内装工事による仕切り壁の設置など、物理的な工事が必要とされるケースが多くありましたが、最近では簡単な仕切りと陳列場所の工夫、棚の配置方法などによって適切に区分されていれば認められる場合が増えていますので大掛かりな工事をせずに実現できるケースは増えているように思います。このような柔軟な対応により、飲食店が以前よりは酒類販売業免許を取得しやすくなっている状況かと思います。
ただし、この基準については税務署や担当官によって判断の厳しさに差があるのも事実です。そのため、自己判断で進めることは避け、必ず事前に管轄の税務署と相談を行い、具体的な区分方法について確認を取りながら進めることが重要です。担当官との十分なコミュニケーションを通じて、確実に要件を満たす形で準備を進めるようにしてください。
レジや売上管理が酒類販売と飲食業で区分できる
飲食店としてお酒を提供する場合と酒販業者としてお酒を提供する場合とで、レジ・売上をしっかりと区分できる必要があります。
レジについてですが、近年はタブレットタイプのレジを含めてPOSシステムのレジが主流かと思いますので、レジそのものを物理的に分けなくてもレジの機能でそれぞれを分けて会計・管理することができるのであればレジそのものは1つでも大丈夫な傾向にあります。
申請時にはレシートサンプルの提出が求められるので、レジ機能についてはしっかりと把握するようにしましょう。
どの免許を取得すべきか?飲食店の場合は一般酒類小売業免許の取得が多い
飲食店が酒類販売業免許を取得するといっても、酒類販売業免許の種類は複数あります。
ただ、飲食店が酒販免許を必要とするケースとしては、同じ店内でお酒を販売したいというものになるので、一般酒類小売業免許の取得が必要な場合が多いでしょう。
飲食店舗内でお酒を販売するなら一般酒類小売業免許が必要
店舗内で一般消費者向けにお酒の販売をしようと思った際は一般酒類小売業免許の取得が必要です。コンビニやスーパーマーケット、酒屋さんなどが取得している免許です。
原則すべての酒類が取り扱えます。
飲食店が酒類販売をするというケースではこの免許が必要な場合が多いでしょう。
飲食店が一般酒類小売業免許を取得する要件は?
飲食業と酒販業を明確に区分することについては冒頭で説明させていただきました。それらが可能であるという前提にたつならば、基本的にその他の要件は通常の一般酒類小売業免許の取得要件と変わりありません。
ただ、明確に区分されていることを証明していかなければならないので、必要書類は多くなりがちです。このあたりは実際の状況に応じて変わってくる部分もあります。
いずれにせよ、通常の一般酒類小売業免許の要件を押させておきましょう。以下ページをご参考ください。
インターネットやカタログ販売するケースでは通信販売酒類小売業免許も必要
インターネットを活用した販売もしたいというケースもあるのですが、その場合は通信販売酒類小売業免許が必要です。
この免許は国産酒を取り扱う場合には制限があり、年間の課税移出数量が3,000kL未満の製造者のお酒でないと販売できません。つまり、大手国産メーカーのお酒は取り扱えないということになります。一方で、輸入酒であれば制限はありません。
店舗でもネットでも販売したいと考えた場合は2つの免許が必要になるということです。免許ごとでやれることや販売できるお酒の種類が異なりますのでご注意ください。
通信販売酒類小売業免許の要件は?
一般酒類小売業免許同様の考え方となりますが、詳細は以下ページをご参考ください。
酒類販売業免許の種類
飲食店が酒類販売業免許を取得するケースとしては、飲食店に来店した方に未開栓のお酒を販売したいということが理由なケースが大半なので、基本的に一般酒類小売業免許の取得で問題ないケースが多いのは間違いありません。
ただ、その他の商流も考えられますので、もし違う販売先や販売方法も検討されているというケースでは以下ページにて酒類販売業免許の種類についても頭に入れておくとよいでしょう。
その他の免許も含め、酒類販売業免許の種類については以下のページをご参考ください。
酒類販売業免許の申請にあたっては税務署とのやりとりや必要書類が多くなり大変になりがち
飲食店が酒類販売業免許を取得するにあたっては、通常の申請よりも必要となる書類が増える傾向にあることから申請作業そのものが大変になります。
また、税務署との相談も増えます。
相談先の税務署は酒類指導官のいる税務署となりますので、最寄りの税務署ではない可能性もあるためご注意ください。
税務署とのやりとりや書類の作成等でお困りであれば行政書士の活用もご検討ください。
各地域によって判断が変わる難しさがある
本ページで記載した事項はあくまで一般的な傾向を踏まえた内容となります。
酒類販売業免許も含めて、行政手続きにおいては地域性もあるため、すべてが同じというわけではありません。
また、飲食店と一口にいってもお店のレイアウトを含めて環境はお店ごとで異なります。
皆様方の置かれている状況によって異なってくるため、しっかりと税務署等とも相談しながら進めていく必要があることにはご注意ください。
アロー行政書士事務所ではお客様の要望に応じたサポートプランを用意しております。
税務署とのやりとりから申請書の作成、提出まで全部やってほしいというケースはもちろん、申請書は自分で作成して提出するから税務署との事前相談や調整・方向性のアドバイスだけやってほしいというケースもあります。
ご状況に応じたサポートを行っております。
酒類販売業免許申請代行・サポートの詳細についてはサービスページも合わせてご覧ください。
お困りでしたらぜひご相談いただければと思います。