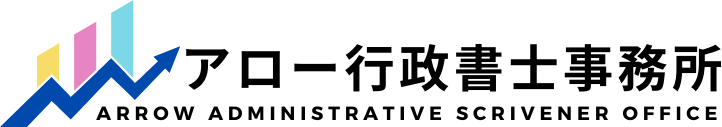お酒のビジネスを始めるにあたっては酒類販売業免許が必要となりますが、事業の開始にあたり、個人で取得するか、はじめから法人で取るかで悩まれる方が一定数いらっしゃいます。
また、近年は副業で酒販ビジネスを始めたいということで、副業の個人の方の相談も多いように思います。
酒類販売業免許は法人はもちろん個人でも取得が可能ですが、法人ではないからこその注意すべき点もあります。
このページでは、個人が酒類販売業免許を取得するために必要なことや注意点について解説していきたいと思います。
アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請のサポート・代行サービスを提供しております。
個人の方で酒類販売業免許の申請でお困りでしたらぜひご相談ください。
酒類販売業免許は個人でも取得可能!副業の個人も増加
酒類販売業免許は個人事業主として問題なく取得可能です。これから個人事業主として開業するというケースでも取得自体は不可能ではありません。
また、新規の法人を設立し、免許申請をすることも可能です。1期目の法人でも取得できます。
たまに個人だと酒販免許が取れないと思っている方もいるのですが、そのようなことはなく、副業の方が個人で酒類販売業免許を取得されるケースも増えているように思います。
副業の方は以下のページもご参考ください。
どのようなお酒をどこから仕入れて誰にどのように販売するのかを決めて必要な酒類販売業免許の区分を検討する
酒類販売業免許を取得するといっても、どの免許を取得するのかによって取得難易度や必要な資料等は変わってきます。
また、どの免許を取得するにせよ仕入先あるいは販売先又はその両方が最低限1つ以上は決まっている必要があります。
申請書を作成するという点でもそうですが、ビジネスを軌道に乗せるという意味でも、お酒をどこから仕入れるのか、どのような方法で販売するのか、誰に対してどこで販売するのかなどは申請前に決定しておく必要があるでしょう。
酒販免許を取得してから仕入先や販売先を見つける、といったことをおっしゃる方もいるのですが、そのような状況だと免許取得はかなり厳しいです。
通信販売酒類小売業免許では国産酒を取り扱うのであれば3,000kl未満の証明書が必要となりますし、酒類卸売業免許の場合は仕入先・販売先の取引承諾書の提出が具体的に求められるため、一定の関係構築は必要です。
個人の場合であれば一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許などの酒類小売業免許の取得を必要とするケースが多いかと思いますが、一般酒類小売業免許でも仕入先を1つは具体的に記載する必要がありますので、酒蔵巡りをしたりするなど、仕入先については1つ以上しっかりとあたりをつけておきましょう。
販売先や販売方法に応じた免許区分を知る
お酒を一般消費者や飲食店向けに小売をするのであれば、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許のように酒類小売業免許が必要となります。
一方で、酒販店やスーパーなどの酒類販売業者、あるいは酒類製造者等へ卸売をするのであれば、洋酒卸売業免許や輸出入酒類卸売業免許のような酒類卸売業免許が必要となります。
先ほど記載したように、誰に対して、どのようなお酒をどうやって売るのかを整理し、必要な免許を見極めていきましょう。
酒類販売業免許の種類については以下のページをご参考ください。
酒類販売業免許申請にかかる費用
酒類販売業免許申請にかかる費用は大きく分類すると以下のものがあります。
①登録免許税:3万円or9万円
②公的書類取得費用:3千円~5千円前後
③酒類販売管理研修費用:5千円前後
④行政書士報酬(行政書士に依頼するなら)
必要書類は個人と法人で若干ことなりますが、個人事業主だから、法人だからという部分で費用は特に大きくは変わらないかと思います。
①の登録免許税については、酒類小売業免許であれば3万円、酒類卸売業免許であれば9万円となります。小売業免許と卸売業免許の両方取得するケースでも最大9万円となります。
個人事業主の場合、一般酒類小売業免許、あるいは通信販売酒類小売業免許の取得を目指すケースが多いので、3万円であるケースが多いかなと思います。
②の書類取得にかかる費用については、個々人(おかれている状況やお店の広さにもよる)によるためあくまで参考値としてご覧ください。
③の酒類販売管理研修は地域により研修費用が異なるのでこちらも参考値となります。
なお、酒類販売業免許申請は結構手間がかかるので行政書士に依頼するケースも少なくありません。
その場合、どの免許を取得するのかにもよりますが、1つの酒販免許申請であれば概ね15万円前後になるかと思います。
個人で酒類販売業免許申請をする際に、概ね経費込みで5万円前後は最低限かかってくるということになります。行政書士へ依頼するならこれに行政書士報酬を追加(15万円前後)してお考え下さい。なお、アロー行政書士事務所の費用については、酒類販売業免許申請サポート・代行サービスページをご覧ください。
費用については以下の記事もご参考ください。
酒類販売業免許取得要件は?個人の場合はご自身の経験・状況がすべて
法人での申請であれば役員全員の経験から要件を満たしていないかを検討していくことができますが、個人事業主の場合、あなたの経験がすべてです。
そういった点も含めて簡単に酒販免許の要件を見ていきましょう。なお、各免許区分によって若干要件が違いますが、ここでは総合的に一般化した内容でみていきたいと思います。
人的要件
ザックリ記載すると税金滞納していないか?過去に何か犯罪歴はないか?といったことの確認となります。個人事業主なのであなた個人についての確認で大丈夫です。
以下は手引きの抜粋となります。
- 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
- 法人が免許等を取り消された場合、取消前1年内に業務執行役員であった者は、取消しから3年を経過していること
- 国税または地方税に関して、罰金刑や通告処分を受けてから3年を経過していること
- 未成年者飲酒禁止法・風営法・刑法等により罰金刑に処せられてから3年を経過していること
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終了した日または執行を受けなくなった日から3年を経過していること
- 免許申請前2年内に、国税または地方税の滞納処分を受けていないこと
場所的要件とは?個人の場合は自宅で免許を取得するケースも多い
個人の場合、意外と店舗や事務所の要件がクリアできずに酒類販売業免許が取得できないケースがあります。
細かく見ていくとキリがないので代表的な例をとると、場所に関しては個人事業主の場合、自分が所有して住んでいるマンションの1部屋を事務所にしたいというケースやレンタルオフィスを事務所にしたいというケースが多いかと思います。
マンションを利用するのであれば、マンションの規約等で事務所利用禁止の取り決めがある場合や仮に事務所可能であっても許認可が必要となるような登録場所としての利用は認めてくれない場合が多くなっています。いずれにせよ、管理組合から承諾書をもらう必要があるので、このハードルが超えられないケースが結構あります。
また、マンションでは無理だからということでレンタルオフィスを検討するケースも多いのですが、レンタルオフィスの場合、賃貸人と建物の所有者が別々というケースが大半であり、この場合において所有者の承諾あるいは所有者と賃貸人との契約がどうなっているのかを税務署が求めてくるので、そこまで開示してくれるあるいは対応してくれるレンタルオフィスもそこまで多くないので、なかなか厳しい結果になってしまうこともあります。
上記はあくまで一例となりますが、こじんまり始めたいケースではなかなかうまくいかないケースもあるため注意が必要です。
なお、地方での免許取得や実家を事務所にというケースでは稀に事務所の地目が農地となっており免許が取得できない場合もあるのでご注意ください。
経営基礎要件とは?
手引きには以下のように記載されていますが、個人の場合は決算書というものがないので、確定申告書を見ていくこととなります。
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合はNG
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合は不可
- 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
※過去にお酒の販売等に関する経験があるか、あるいは知識があるか、経営経験等があるかは総合判断されます。 - 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
※一定の資金が必要です。
個人事業主であれば3期分の確定申告書や給与所得を得ているケースだと源泉徴収票を提出し、判断してもらうことになるのですが、明らかに赤字が大きすぎるといったことがなければ大丈夫かと思います。まだ確定申告をしたことがないという場合であれば確定申告書の提出は不要です。
実務経験については、手引きをよく読むと3年以上の経験・経営経験など具体的に年数が指定されているようにも見えるのですが、必ずしも3年ないとダメとうこともありません。
あなた個人のこれまでの経験を総動員して要件クリアを目指していくことになります。
なお、法人であれば、法人役員全員分の経験値を見ることができるので、経験が少ない場合は法人の方が免許が取りやすいこともあります。
どこから仕入れてどこに売るのか
仕入先・販売先はやはりある程度1つは決まっている必要があります。
お店やインターネットで一般消費者へ販売するということであれば販売先は来店した方で問題ありませんが、仕入れをどうするのか?という問題はあります。申請時点で最低1つは必要なので、仕入先を開拓するようにしましょう。
個人で申請する場合の必要書類一例
個人でも法人でも基本的に必要書類は同じですが、法人の場合は定款や決算書等が必要となりますが、個人にはありませんので確定申告書類が代わりに必要となります。
【必要書類例】
申請書、次葉1~6(販売場敷地状況、建物等配置図、事業概要、収支見込表、資金、酒類販売管理取組計画書)、誓約書、履歴書、地方税納税証明書、確定申告書・源泉徴収票(給与所得がある場合等)、土地建物登記事項証明書、賃貸借契約書・所有者の承諾書
等
履歴書などは法人であれば役員全員分必要ですが、個人であれば本人のみで大丈夫ですので、個人で申請する場合の方が必要書類は少ない場合が多いかと思います。
なお、上記はあくまで例です。ご状況等にもよるところはあります。
個人で酒類販売業免許を取得した後に法人化(法人成り)する際は手間はかかることに注意
個人で酒類販売業免許を取得し、売上が大きくなってきたら法人化を検討したいというケースもあろうかと思いますが、個人から法人成は可能です。
ただ、法人成りの手続きがあるわけではありません。
個人で取得した免許を法人に引き継ぐ手続きがあるわけではなく、法人で新規に免許を取得しなおすという流れとなります。なので、新規申請をもう一度行うということで手間は結構かかります。登録免許税も新たにかかります。
内容を引き継ぐにあたっては、同じ免許を取得することで対応する形となりますが、実質的に新規で申請をする必要があることにご注意ください。また、法人で免許が取れたらその段階で個人の方の免許は取り消しをする措置も必要です。つまり、結構手間がかかります。
既に一度免許を取得しているので、初めて申請するよりは手間はかからないかもしれませんが、ちょっとした書類を出したら法人成できるというものでもないのでご注意ください。
個人・法人のメリット・デメリット
たとえば、副業でお酒の販売を始めるというケースでは最初から法人化するメリットはないケースが多いかと思います。
法人の場合、法人設立にかかる費用、維持費などが大きくかかってくるので、そこが大きなデメリットになるかと思います。個人の場合であればかからない費用がかかってくることになります。
ただ、個人よりも法人の方が信用力は一般的には高いため、しっかりとしたビジネスをやっていくという視点で見た際は法人の方がやりやすいというのはあるかと思います。
なお、あくまで傾向・一例となります。
■メリット・デメリット
個人は開業がしやすく、ランニングコストが安い。決算(確定申告)も自分で可能。信用力は法人と比べると低い。
法人は法人設立費用もかかり、ランニングコストが個人と比べると高い。決算申告も税理士にお願いする必要が基本的にある。個人と比べると信用力は高い傾向。
飲食店を運営する個人事業主が同じ場所で酒類販売業免許を取れるか?
原則として居酒屋等の飲食店では酒類販売業免許は取得ができません。
ただ、一定の条件を満たすことで免許が取得できるケースも多くなっています。ハードルが高いため、やや苦戦する傾向にありますが、不可能ではない場合も多くなっています。
飲食店が酒類販売業免許を取得するケースについては以下のページをご参考ください。
個人事業主が取得する酒類販売業免許はどれ?
個人事業主の場合、酒類小売業免許の取得が大半です。
一般酒類小売業免許
一般消費者や飲食店向けにお酒を販売されるケースは非常に多いため、個人でも一般酒類小売業免許の取得はそれなりにあるでしょう。
個人で酒販店を営んでいるケースはそれなりにあるので免許取得の需要は高い傾向です。
通信販売酒類小売業免許
副業で酒類販売業免許を取得するという個人の場合は通信販売酒類小売業免許の取得が多いでしょう。
スモールビジネスで小さく始めるにあたってはネット販売から入っていくケースは多いかと思います。
後は、経験が浅くても比較的免許が取りやすいということもあります。
酒類卸売業免許各種
酒販業者向けに卸売をするというケースもあるかもしれませんが、その場合は卸売業免許が必要となります。
基本的に法人が取得するケースが多いかと思いますが、自己商標卸売業免許や輸出入酒類卸売業免許は個人の方でも取得するケースはあるかと思います。
個人でも酒類販売業免許は取得できるが将来法人化を検討しているなら注意しよう
個人事業主だと酒類販売業免許は取得できないと勘違いしているケースもありますが、そのようなことはなく、要件を満たし、必要な条件がそろっていれば可能です。
本格的に大きくしていくつもりで事業として始める方はもちろんですが、まずは副業から始めていきたいとお考えの方や定年後に小規模でお酒の販売ビジネスをやろうと考えている方は一定数いらっしゃり、個人で酒販免許を取得されるケースはあります。
もし個人の方で酒類販売業免許の申請でお困りでしたらぜひご相談いただければと思います。
酒類販売業免許申請代行サービスのページもあわせてご覧いただければと思います。
お問い合わせやご相談は以下よりお願いします。