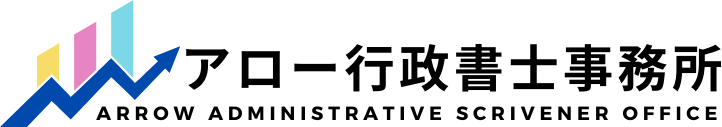大好きなワインの販売を始めたい!そんな想いを胸にワインビジネスを始めようとする方も多いのですが、ワインを販売する際に避けて通れないのが酒類販売業免許の取得です。
一口に「ワインの販売」と言っても、街のワインショップのような店舗で販売するのか、それともワインバー等のような飲食店と併設してのワイン販売なのか、あるいはインターネットで一般消費者向けに販売するのかなど、ワインを販売する方法や販売する対象によって取得すべき免許の種類は異なります。
ご自身のビジネスプランに合う酒類販売業免許を申請する必要があります。
そこでこのページでは、これからワインの販売ビジネスを始めたいと考えているあなたのために、酒類販売業免許の種類について解説します。店舗販売、通信販売(インターネット販売)、さらには輸出入に必要な免許まで、あなたの目指す販売形態に最適な免許がどれなのか、しっかりと把握するようにしましょう。
なお、アロー行政書士事務所ではワインに関わらず酒類販売業免許の取得サポートを行っております。酒販免許の申請でお困りであれば、ぜひ酒類販売業免許申請代行サービスもご利用ください。
※本ページはあくまで未開栓のワインを販売するのに必要な酒類販売業免許申請に関する解説となります。飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出など飲食店をこれから開業される方向けの内容ではありませんのでご注意ください。ただし、これらの事業者が酒類販売業免許を必要とするケースについては解説をしております。
ワインをどこから仕入れ、誰に対して、どのように売るのかで必要な酒類販売業免許が違う
ワイン販売にあたって酒類販売業免許が必要なことはほとんどの方がご存知かと思いますが、酒類販売業免許と一口にいってもさまざまな種類があります。
一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、輸出入酒類卸売業免許、洋酒卸売業免許などがあり、内容に応じて必要な免許が異なります。
「どこからワインを仕入れ、誰に対して、どのように販売するのか」によって必要な免許が変わってくるので、まずは商流を整理する必要があるでしょう。
また、そもそもどういった免許があるのかを知っておく必要もあるでしょう。
お酒の販売に必要な酒類販売業免許は大きく「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つにわかれています。
酒類小売業免許とは?
「酒類小売業免許」は、一般消費者や居酒屋・レストラン等の飲食店へワインを販売するために必要な免許です。
例えば、あなたが街でワインショップを開いて一般消費者に販売する場合やインターネットで個人のお客様に販売したりする場合は、「酒類小売業免許」を取得することになります。仕入先としては、酒類卸売業者や国内外のワイナリーから直接仕入れる形が一般的です。
この酒類小売業免許も販売形態に応じて「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」といった形で複数の免許区分に分かれています。
一般酒類小売業免許は1つの都道府県内で一般消費者や飲食店向けに酒類を販売する際に必要となる免許で、通信販売酒類小売業免許は2都道府県以上にまたがってネット販売などの通信販売によりお酒を販売する際に必要となる免許です。
酒類卸売業免許
一方、「卸売業免許」は、スーパーマーケットや酒屋、他のワイン販売業者など、すでに酒類販売業免許を持っている事業者に対してワインを販売(卸売)する場合に必要となります。
例えば、あなたが海外のワイナリーから直接ワインを輸入し、それを国内の様々な酒販店に卸したいといったビジネスモデルはこちらの免許に該当します。
輸出入酒類卸売業免許や洋酒卸売業免許、ビール卸売業免許、全酒類卸売業免許など酒類卸売業免許もさまざまな種類があります。
あなたのビジネスプランにおいて、お酒を「消費者(飲食店含)に届ける」のか、「酒類事業者に販売する」のか、あるいはその「両方」なのか等によって取得すべき免許の方向性が異なります。まずはご自身の事業計画を明確にし、どの免許が必要になるのかを正しく見極めることがワインビジネス成功への第一歩と言えるでしょう。
酒類販売業免許各種について解説すると長くなりますので、免許の種類について詳しく知りたい方は以下のページで詳細をご覧ください。
このページではワイン販売にあたって必要となると想定される免許区分に絞ってケースごとにみていきたいと思います。
ワインを販売しようと思った際に必要となる酒類販売業免許の種類をパターン別に解説
ワインの販売にあたって必要となる酒販免許を希望やお悩みごとに見ていきたいと思います。
なお、あくまで大まかな記載となりますので、ご状況によっては異なる免許が必要となることがあることはご了承ください。
国内・海外のワイナリーからワインを仕入れ、店舗を構えて一般消費者に販売する場合は一般酒類小売業免許が必要
店舗を構え、お店に来た人に対してワインを販売する最もスタンダードな形を考えている場合は一般酒類小売業免許が必要です。
一般酒類小売業免許は原則すべての酒類を取り扱うことが可能な免許なのでワインも販売可能です。
なお、国内のワイナリーから仕入れる場合だけでなく、海外から輸入するケースであっても、国内の一般消費者や飲食店向けの販売であれば、輸入酒類卸売業免許は不要です。
レストランなどの飲食店専門にワインを販売する場合も一般酒類小売業免許が必要
店舗を持たずに飲食店等専門に配達でお酒を販売するビジネススタイルも一定数ございます。
この場合においても一般酒類小売業免許で問題ありません。
ただし、一般酒類小売業免許は1都道府県内のみで販売することが前提となっているので、2都道府県以上に配達でお酒を販売する場合は、管轄の税務署によりけりですが通信販売酒類小売業免許の取得が求められるケースも多くなっています。申請する地域により異なるケースがあります。
仕入れたワインをネットで販売するな通信販売酒類小売業免許が必要
ECサイト等を構築し、ネット上でワインを販売するのであれば通信販売酒類小売業免許が必要です。
ただし、この免許は販売可能な酒類に制限があります。
輸入酒であれば販売可能な酒類の品目に制限がないため、輸入ワインであればネット上で問題なく販売することが可能です。
一方で、国産ワインの場合は課税移出数量3,000kl未満の酒類販売事業者のものしか販売することができません。そのため、大手酒類メーカーのワインはネット販売が基本的にできないこととなります。実際に免許申請の際に仕入先から3,000kl証明書を出してもらい、税務署へ提出が必要です。
なお、上記に該当する場合においても、地方特産品等を原料として酒類製造して販売するケースにおいては、製造数量年間3,000kl未満であれば通信販売が可能となっています。
ワインを海外から輸入して酒類販売業者等に卸売するのであれば輸入酒類卸売業免許が必要
自社で海外からワインを輸入し、酒類業者へ卸売するのであれば、輸入酒類卸売業免許が必要です(※洋酒卸売業免許でも可)。
なお、税務署の酒販免許申請の手引きを見ると「輸出入酒類卸売業免許」と記載されておりますが、輸出と輸入は別々の免許区分になるのでご注意ください。
また、先ほど記載したように、輸入したワインを一般消費者や飲食店向けに直接販売するのであれば卸売業免許は不要で、小売業免許で対応が可能です。
他の酒販免許事業者が輸入したワインを仕入れてそれを更に別の酒販業者へ卸売りする場合は洋酒卸売業免許が必要
洋酒卸売業免許は、洋酒であれば国産・海外産問わず卸売が可能な免許となります。
ワインは洋酒(※税法上ワインは果実酒・甘味果実酒という品目)にカテゴライズされるため、ワインを他の酒類事業者から仕入れて卸売しようと思った際は洋酒卸売業免許が必要です。
輸入も含めてワインしか扱わないのであれば洋酒卸売業免許が取得できればそれに越したことはないかもしれません。
ただし、取得要件は輸入酒類卸売業免許より洋酒卸売業免許の方が高いです。
輸入したワインを酒屋等の酒販免許業者と一般消費者等の両方に販売するなら輸入酒類卸売業免許等の卸売業免許と一般酒類小売業免許等の小売業免許が必要
ワインを自社で輸入し、卸売と小売両方するのであれば、両方の免許が必要です。
一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、輸入酒類卸売業免許の3つを申請するケースもあります。
3つまとめての申請であればまとめて申請する分手間が省ける為、アロー行政書士事務所で申請するケースではまとめて申請する場合の割引も行っております。
ワインバーやレストランと併設してワイン販売をやりたいなら一般酒類小売業免許が必要だが原則として飲食店は酒類販売業免許は取れず、申請においては工夫が必要
よくある質問として、飲食店営業許可や深酒の届出をしているレストラン等の飲食店を経営している方から酒類販売業免許も取得したいということでご相談いただくケースがありますが、原則として飲食店は酒類販売業免許を取得できません。
ただ、いくつかの要件を満たすことができれば、酒販免許申請が可能です。
具体的には、お酒の販売場と飲食スペースがしっかりと区分できる、飲食用のお酒と酒類販売用のお酒の管理がしっかり区分できる、お会計もそれぞれしっかり区分できるといった形で、飲食と酒販をしっかりと区分することができるかどうかがカギとなります。
お店の間取り、スペース、人員体制など含めて細かく見ていく必要があるので、免許取得のハードルは高いのですが、ワインバー等であれば気に入ったワインを買っていきたいというお客様も多いかと思うので、一定の需要があります。
手間はかかりますが、頑張れば免許取得も不可能ではありませんので、飲食店等で酒販免許を取得したい場合はぜひご依頼いただければと思います。また、参考として以下のページもご覧ください。
ワイン販売にかかる免許申請にあたって仕入先を確保しておく必要がある
ワインを販売したい!という希望をお持ちの方は多いのですが、仕入先のあてが全くないという方も珍しくありません。
酒類卸売業免許であれば仕入先・販売先から承諾書を取得する必要があるので、ある程度仕入先は固まっている必要があります。
酒類小売業免許でも仕入先は最低1つは定まっている必要がありますので、どこから仕入れてどこに売るのか、しっかりと検討してください。
とりあえず免許を取ってから仕入先等を探す、ということはできませんのでご注意ください。
ワイナリー巡りをするなど、しっかりと酒類製造者等と関係性を構築するようにしましょう。
輸入や輸出をするなら輸出入の業務経験や語学力が見られる場合も
ワインを輸入して国内で販売したいというケースのほか、近年はアジアへ日本のワインを輸出したいというケースも一定度増えているように思います。
輸出・輸入酒類卸売業免許を取得するにあたっては、お酒の販売に関する業務経験というよりも輸出入の業務経験あるいは知識の有無等も重要です。
輸出・輸入に関する手続きがしっかりとできるのか?理解しているのか?といった部分も要件を満たすのに必要となる場合もあるため、輸出・輸入に関しては、基本的に現在貿易関係の実務を行っており、お酒の販売もやろうというケースで取得される場合が多くなっています。
酒類販売業免許の申請はハードルが高いためぜひ行政書士へご相談ください
申請さえすれば誰でも免許とれるんでしょ?と思っている方も結構多いのですが、酒類販売業免許は意外と要件が高く厳しいため、残念ながら取得できないという方も珍しくありません。
ご自身で申請する際はもちろんですが、行政書士に相談した結果取得は無理ですねと言われてしまうケースもあるようです。
ただ、これまでの経歴等をしっかりと棚卸をし、どうにか要件を満たせていないか検討していくことでクリアできるケースも多くございます。
そのため、税務署との事前相談や行政書士への相談で無理だと言われてしまったケースでもぜひ一度ご相談いただければと思います。
冒頭でも記載しましたが、アロー行政書士事務所ではワイン販売を含め、酒類販売業免許申請のサポートをしております。
お困りでしたらぜひ酒類販売業免許申請代行サービスの利用をご検討ください。
酒販免許取得に向けて一緒にがんばりましょう!