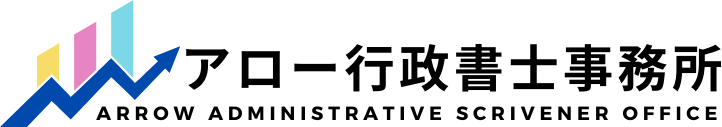アロー行政書士事務所では古物商許可申請をサポートさせていただいておりますが、よくある相談として、お酒の買取・販売もしたいけど古物商許可で問題ないのか?というものがあります。
残念ながら、お酒の売買にあたっては、古物商許可ではなく、販売先・販売形態に応じた酒類販売業免許が必要となります。
ここでは、古物商許可業者がお酒の買取・販売も検討した際に必要となる許可あるいは免許について簡単に解説していきたいと思います。
なお、アロー行政書士事務所では古物商の許可申請も酒販免許申請もどちらも取り扱っておりますので是非ご相談ください。
古物商許可ではお酒の販売はできない!酒類販売業免許が必要
結論からお伝えすると、古物商許可を取得していてもお酒の販売はできません。古物商がお酒を販売するためには、別途「酒類販売業免許」などのお酒を提供するための免許や許可が必要となります。
お酒の販売方法はいくつかパターンがあります。
例えば、レストランや居酒屋などで開栓したお酒を提供するというケースが考えられますが、この場合は「飲食店営業許可」が必要です。一方で、未開栓のお酒をスーパーマーケット等の店舗で販売する場合には「酒類販売業免許」が求められます。
古物商の場合、通常は後者に該当することになりますので、酒類販売業免許が必要だということになります。
また、酒類販売業免許と一口に記載しましたが、酒類販売業免許も免許区分がいくつかあります。
古物商として他の商品と合わせてお酒も扱いたいというご相談をいただくことがありますが、買い取ったお酒を販売するにあたり、その販売方法や販売対象にマッチした酒販免許が必要です。古物商許可のみでは対応できないというのはもちろんですが、どの酒販免許を取得するのかということも重要です。
酒類販売業免許の申請先は税務署で取得のハードルは高い
古物商許可が警察署への申請だったのに対し、酒類販売業免許は税務署が申請窓口となります。申請書を提出すれば完了というわけではなく、税務署の担当者と何度もやりとりを行いながら手続きを進めていく必要があります。
古物商許可と比較すると審査基準がはるかに厳格で、提出書類の種類も多く、審査過程も非常に詳細に行われます。そのため、「申請さえすれば誰でも取得できる」というような性質のものではなく、実際に免許取得に至らないケースも珍しくありません。
また、先ほど記載したように「酒類販売業免許」と一言で表現しても、実際には販売スタイルや販売対象によって複数の免許区分に分かれており、自身のビジネスモデルに最適な免許区分を選択して申請することが大切ですので、どの免許が必要なのかを判断するのも意外と大変です。
お酒を買取りするだけなら酒類販売業免許は不要で古物商許可だけでも大丈夫
「酒類販売業免許」は、その名の通りお酒を販売する際に必要な免許です。そのため、お酒を買い取るだけの行為であれば、原則として酒販免許は必要ありません。また、お酒はその性質上、基本的に古物営業法の対象外となっているので、お酒の買取のみを行う場合であれば古物商許可も不要と考えられています。
しかし現実的には、「買取=将来的に販売する」という前提で事業を行うケースがほとんどです。実際に販売を開始する段階では、仕入れルートや販売先、販売方法によって取得すべき酒販免許の種類が決まってきます。
酒類販売業免許は「小売業免許」と「卸売業免許」の2つに大別されます
ここまでで、酒類販売業免許の種類がいくつかあることは記載してきましたが、大きく分類すると「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに分けることができます。さらに、酒類小売業免許は「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」、酒類卸売業免許は「洋酒卸売業免許」「輸出入卸売業免許」などといった形でより詳細な免許区分に細分化されています。
小売業免許と卸売業免許の違いを簡単に説明すると、一般の消費者に向けて販売する場合は「酒類小売業免許」、酒類を扱う事業者に向けて販売する場合は「酒類卸売業免許」が必要ということになります。
古物商許可業者の場合、一般消費者への販売がメインとなることが多いため、酒類小売業免許のカテゴリーから適切な免許を取得するケースが一般的です。
以下では実際によくある販売パターンに応じてどのような免許が必要になるかを具体例とともにご紹介します。
※販売形態や取扱商品、事業規模などによって要件が異なる場合があるため、あくまで参考としてご活用ください。
店頭で一般消費者を相手に販売をするなら一般酒類小売業免許が必要
買取店舗でお酒の販売も行いたい場合は「一般酒類小売業免許」が必要です。
これは、店頭で一般の個人や飲食店などに対して未開封の酒類を販売するための免許で、いわゆる酒屋さんやコンビニ、スーパー等が取得している免許です。
古物商としてお酒を売りたいと考える方の多くがここに該当しますが、誤って「卸売業免許が必要」と思い込んでしまうケースも見受けられるため、注意が必要です。
また、酒販免許は販売場(店舗)ごとに取得が必要です。
たとえば複数の買取店舗で酒類を販売する予定がある場合は、各店舗ごとに免許の申請・取得が必要になります。
注意すべきなのは、酒類販売業免許における店舗要件は、古物商のそれよりも厳しいという点です。
古物商許可と異なり、事務所の賃貸借契約書の記載事項までしっかりチェックされますので、契約内容によっては厳しい場合があります。
また、賃貸人とは別に所有者がいる場合においては必要書類が更に増えることもあるなど、取得が難しいこともあります。
インターネット上でお酒を販売するなら通信販売酒類小売業免許が必要
インターネットやネットオークション、カタログ販売を検討している場合は、通信販売酒類小売業免許が必要です。古物の売買も最近はネット上で行うケースが多いかと思いますが、お酒も同様にインターネット上で販売するケースが増えています。
なお、一般酒類小売業免許と異なり、取り扱いできる酒類の範囲に制限があります。古物を取り扱うお店がお酒も取り扱うという視点で見た場合、輸入酒を取り扱うケースが多いので問題とならないケースもありますが、免許ごとで取り扱い可能なお酒の種類があるのでご注意ください。
参考として、通販免許の場合、輸入酒は制限が基本的にありませんが、国産酒は課税移出数量が3,000kℓ未満のでないと販売ができません。なので、大手の国産のビールメーカーのビール等は販売ができないこととなります。
また、3,000kl証明書も必要なので、酒類製造メーカー等とのつながりも必要です。
なので、古物商の場合は輸入酒の取扱いがメインになるケースが多いかと思います。
酒類販売業者等に販売するなら該当する酒類卸売業免許が必要
買取り・販売という視点において、卸売業の免許が必要となるケースはそこまで多くありません。ただ、酒類販売業者等に販売するケースがあるなど、一定の場合において必要となることがあります。
一般消費者以外にも販売する可能性がある場合は検討してみてください。なお、卸売業免許も複数あるため、どこに何を卸すのかを整理したうえで免許申請する必要があります。
各免許区分について細かく知りたい方は以下の記事をご参考ください。
古物商がお酒の販売をしたいと考える場合、基本的には一般酒類小売業免許か通信販売酒類小売業免許が必要となることが多い
上記で説明した通り、古物商許可が必要な方がお酒の販売も使用と思った際は、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の両方、あるいはどちらかが必要となるケースが多いでしょう。
一般酒類小売業免許は取得のハードルが高いため、通信販売酒類小売業免許の場合が多いかなとは思います。
アロー行政書士事務所ではこの2つの申請を同時に行う場合に大きく割引して対応しておりますので、酒販免許申請でお困りでしたらぜひご相談ください。
なお、酒販免許は古物商許可と違って取得要件・ハードルが高めであることから、断念せざるを得ないケースもかなり多くございます。そのため、まずは免許が取得できる状況なのかということをしっかりと確認させていただければと思います。
また、やりたいことが実現できるかどうかも重要です。
仕入先・売り先・販売するお酒の種類などによって必要な免許は変わってきます。申請さえすればなんでも免許が取れるというものでもありませんので、やりたいこととできることを整理していくことも重要です。
なお、これから古物商を始めるという方であれば、古物商許可申請も対応することが可能です。
段階的に酒販免許を取得していくという方法も
酒販免許は免許ごとに要件が微妙に異なります。
たとえば、一般酒類小売業免許で申請したかったとしても、経営経験不足により申請が難しい場合も多くなっています。
ただ、通信販売酒類小売業免許なら要件を満たせそうだという場合もあります。
なので、初めに通販免許を取得し、実績を得たうえで一般酒類小売業免許も後々に取得していくといった方法を取ることもあります。
直近・先々の経営方針も見ながらうまくやっていく方法も考えられるでしょう。
お酒の瓶そのものに価値があり、骨とう品要素がある場合は古物に該当するケースも
お酒は古物営業法の対象外なので基本的にお酒の売買において古物商の許可が関係してくることはありません。
ただ、お酒の瓶等に骨董品的な価値があり、それそのものが骨董品として売買されるケースというのもゼロではありません。
このお酒の瓶を売るというケースでは酒販免許ではなく、古物商の許可が必要となってきます。
単純にお酒の瓶の売り買いであればいいのですが、じゃあ中身が入っていて瓶に価値のあるお酒を取扱うなら?など少々微妙な線引きとなるものも出てくるかと思いますので一定の注意が必要な場合もあります。こうしたケースでは管轄の警察署等でも念のため確認を入れておくのが良いでしょう。
迷う場合はご相談いただければと思います。
お酒を扱うなら古物商許可ではなく販売形態・お酒の種類等に応じた酒販免許が必要
冒頭にも記載しましたが、お酒を販売するなら、適切な酒類販売業免許が必要です。
そして、古物商許可と違って酒販免許申請はかなり複雑で難易度が高いです。
自分に必要な免許が何なのか迷うケースもあるかと思います。
そのため、古物商許可の申請は自分でやるが、酒販免許の方はお願いしたいというケースも多くなっています。
酒類販売業免許申請代行・サポートサービスページもぜひご覧ください。
本ページでは詳しく許可要件や条件を記載しませんでしたが、申請すれば誰でも免許が取得できるというものでもありませんので、古物商とあわせて酒類販売業免許が必要という方はぜひご相談いただければと思います。