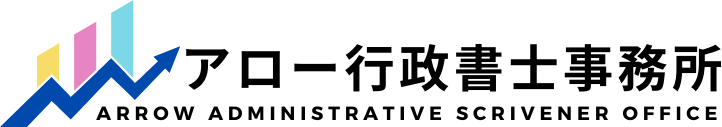洋酒卸売業免許とは、文字通り「洋酒」を卸売する際に必要となる免許です。
洋酒であれば国産か輸入酒かは問いません。
酒類卸売業免許の中でも洋酒卸売業免許の相談が一番多いかなと感じますが、このページでは洋酒卸売業免許について解説していきたいと思います。
アロー行政書士事務所では洋酒卸売業免許をはじめとして各種酒類販売業免許申請をサポートしております。
洋酒卸売業免許の申請でお困りでしたらぜひご相談ください。
洋酒とは何を指すのか?
洋酒卸売業免許というと輸入したお酒など、海外のお酒を卸売りするのに必要な免許だと思う方もいらっしゃるのですが、そうではありません。
冒頭で記載したように、国産・海外産問わず「洋酒」にカテゴライズされる酒類を卸売することができる免許となります。
洋酒とは以下の酒類を指します。
【品目】
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒
【例】
果実酒:ワイン
甘味果実酒:ベルモット、シェリー
スピリッツ:ジン、ウォッカ
リキュール:梅酒、キュラソー、カクテル
ワインやウイスキー、ジン、ウォッカ、カクテルなどを卸売しようと思ったら洋酒卸売業免許が必要であるということです。
当然ですが日本酒(清酒)は洋酒ではありませんのでこの免許区分には入りません。
また、ビールも洋酒卸売業免許では取り扱えないこととなります。なので国産はもちろんですが海外のビールを卸売したいと思った際は別の免許が必要になるということです。
なお、洋酒卸売業免許を取得すれば上記に記載した洋酒にカテゴライズされるすべての酒類を取り扱えるわけではなく、指定された品目のみ取り扱えるという形になります(近年は自動的に全品目指定してくれるケースが増えておりますが税務署・担当官によりけりです)。
卸売とは?
洋酒「卸売」業免許なので、卸売をするための免許であり、小売することはできません。
ここでいうところの卸売とは、酒類販売業者や酒造業者への販売を指します。なので、既に何らかの酒販免許を持っている酒類業者などへ販売することを卸売というのだとザックリでいいのでご認識いただければと思います。
小売とは、店頭やインターネットなどを活用して一般消費者へお酒を販売するケースや、レストラン・居酒屋などの飲食店へお酒を販売するケースを指しています。
よくある勘違いとして、飲食店へお酒を卸したいから洋酒卸売業免許が欲しい、といった相談を受けることがたまにありますが、この場合は卸売ではなく小売に該当するので洋酒卸売業免許ではなく一般酒類小売業免許などの酒類小売業免許が必要になるということになります。
やりたいことによっては卸売業免許と小売業免許の両方を取得する必要がある場合もあるでしょう。
卸売業免許・小売業免許の違いを含め、詳細は以下ページに記載しておりますのでご参考ください。
洋酒卸売業免許とはつまり?
上記に記載した内容をまとめると洋酒卸売業免許とは、
国産酒か輸入酒か問わず、洋酒(果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒)を酒販店などの酒類販売業者や酒類の製造者へ継続的に販売することができる免許です。
ワインやブランデー、ウイスキーを卸売する場合はこちらの免許が必要だということです。
なお、指定された品目であれば輸入することも可能です。
洋酒卸売業免許取得要件は?
洋酒卸売業免許を取得するにあたっては、場所的要件、経営基礎要件などをクリアする必要があります。審査要件をすべて記載するととんでもない量になるので、ここでは主なものに絞って解説していきます。
※あえてかみ砕いた表現をしています。正確な記載は税務署の手引きをご参考ください。
経営基礎要件
経営基礎要件とは、ザックリ記載すると、会社(あるいは個人)が税金を滞納していたり、債務超過になっていたりしないかを確認するものです。
特に引っかかりそうな部分としては、
・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていないこと
・最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと
上記があげられます。大まかに記載すると、直近のBS・PL上で大きな繰越損失(繰越利益剰余金がマイナス)がある、3期連続でそれなりの赤字が出ているといったケースでは注意が必要です。
顧問税理士がいるのであれば、決算書から要件を満たしていそうか確認するとよいでしょう。
経験に関する要件
これも大まかに記載すると、役員(個人事業主なら事業主)に関して、お酒に関する業務経験が3年以上ある、経営経験がある(経営能力がある)といったことが求められます。
法人の場合は役員全員の経験を総合して考えることができるので、代表者の方にお酒の販売関係する経験がなかったとしても免許取得は可能です。
また、この経験値に関する項目は絶対的なものではありません。手引きを読めばわかりますが、若干曖昧な記載になっているので、自分は該当するだろうか?と疑問に思うようなケースでも免許が取得できるケースはあります。
良くも悪くもやりよう次第の項目となります。役員間でしっかりと話をすることも重要でしょう。
場所的要件
意外とネックになることがあるのが場所に関する要件です。
具体的な要件というよりかは、承諾書が取れないなどの問題に遭遇することが一定数あります。
卸売業免許の場合はそこまで多くありませんが、自分が所有するマンションの1室で免許を取得しようと思った際は管理組合等からの酒類販売業を行うことに関する承諾書の提出が求められます。
また、オフィスを賃貸して借りているケースにおいて「事務所」としての利用用途で借りているケースでも承諾書(ビル等の所有者から)が求められるケースもあり、なかなかうまくことが運ばないといったこともあります。
稀に事務所予定地の地目が農地になっているケースがあるのですが、農地では免許が取れませんのでご注意ください。
場所に関する要件もいろいろあり、現在借りているところでは要件を満たせないというケースもあるためご注意ください。
酒類卸売業免許は取引予定先との取引承諾書の提出が必要
洋酒卸売業免許を含め、酒類販売業免許を取得したいという方の中には、販売先や仕入先の目途が全くたっていないという方もいらっしゃいます。原則として、取引先が定まっていないと免許を取得することはできません。
卸売業免許では、免許が取れた際は取引の予定があることを証明する取引承諾書が必要となります。
免許が取れてから探そうと思っていた、という方もいらっしゃるのですが、それは難しいためご注意ください。
洋酒卸売業免許は9万円の費用(登録免許税)がかかる
洋酒卸売業免許は登録免許税9万円となります。
小売業免許は3万円の登録免許税、卸売業免許は9万円の登録免許税となりますが、仮に別の酒販免許も一緒に取得する場合でもあっても納める必要のある費用は9万円までとなります。
ただし、販売場ごとに登録免許税が必要となりますので、他の販売場でも免許を取得する場合は免許場所ごとに納める必要があることにご注意ください。
必要書類
洋酒卸売業免許の申請にあたって必要となる書類は、申請者の状況によって変わってきます。
一般的には以下のものが求められます。
申請書、次葉1~5(販売場図、配置図、事業概要、収支見込、資金)、誓約書、定款の写し、履歴書、取引承諾書、賃貸借契約書や承諾書、納税証明書(都道府県・市町村)、決算書、、、等
なお、法人の場合は役員全員の履歴書等が必要となりますが、履歴書の書き方にも注意が必要です。
洋酒卸売業免許申請にあたっては行政書士への依頼も
洋酒卸売業免許をはじめとして、酒販免許申請は意外と手間がかかります。
必要書類が多い他、作成にも一定のポイントがあります。また、承諾書をどうすればいいのかなど戸惑う部分もあるでしょう。
免許申請をする以前に、自身に必要な免許が何なのか意外とわかりにくく、悩むケースもあるかと思います。
アロー行政書士事務所では洋酒卸売業免許をはじめとして各種酒類販売業免許申請をサポートしております。
洋酒卸売業免許の申請等でお困りでしたらぜひご相談いただければと思います。
酒類販売業免許申請の代行・サポートに関しての詳細や料金はサービスページもあわせてご覧ください。
洋酒卸売業免許の申請をご検討されている方はぜひご相談いただければと思います。。