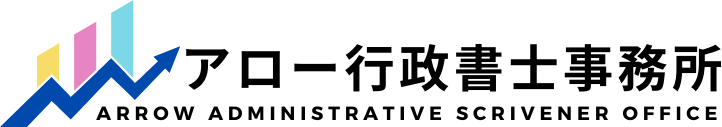インターネット(ECサイト)を活用して海外へお酒を販売したい!貿易業を行っているが酒類の輸出にも取り組んでいきたいなど、お酒を輸出販売するための免許取得を目指すケースが増えております。
日本酒ブームはもちろんですが、近年は日本のワインをアジアへ輸出する、日本のウイスキーの人気の高まりから輸出を検討しているなど、輸出の際に必要となる輸出酒類卸売業免許に関するお問い合わせは増加しております。
このページでは、そんなお酒の輸出を検討されている方向けに輸出酒類卸売業免許や関連する酒販免許について解説していきたいと思います。
アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請の代行・サポートサービスを提供しております。
酒販免許申請でお困りでしたらぜひご検討ください。
輸出酒類卸売業免許でできること
輸出酒類卸売業免許は、自社(自己)が直接海外の酒販業者や消費者等へ輸出することができる酒販免許です。全酒類取り扱えるのが大きな特徴といえるでしょう(指定された品目に限りますが近年はすべて指定されるケースが増えているかと思います)。
なお、輸出以外の卸売はできませんのでご注意ください。国内の酒販業者や一般消費者へ販売しようと思った際はその他の酒類卸売業免許、あるいは酒類小売業免許が必要となります。
また、税務署の手引きには、「輸出入酒類卸売業免許」と記載されているので勘違いされている方も稀にいらっしゃるのですが、輸出と輸入はそれぞれ免許がわかれていることにご注意ください。輸出酒類卸売業免許を取得しても輸入はできません。
輸出酒類卸売業免許はあくまで輸出で必要な免許なので輸入も必要という場合は輸入酒類卸売業免許やその他の該当する免許の申請もあわせて検討してください。
輸出酒類卸売業免許の要件
輸出酒類卸売業免許は、酒類卸売業免許の中では比較的要件は軽い方だと言えるでしょう。酒類販売の経験が必須ではないためです。
要件については細かく記載すると膨大な量になってしまうため要点をかいつまんで記載させていただきます。実際の申請の際はしっかりと細かくチェックさせていただきます。
税金の滞納や大きな赤字・損失を出していないこと
税金を滞納していないこと、銀行と取引停止になっていないことといった基本的な要件のほか、直近の確定した決算において大きな損失が出ていないこと(繰越損失が資本等の額を上回っていないこと)や直近3期の決算において資本等の20%を超える赤字を連続でだしていないかなどといった条件があります。
決算の要件がクリアできずに免許取得をあきらめるケースというのも少なからずありますが、まずは自社の経営状況についてチェックしてみてください。
なお、個人や新設法人の場合は過去の決算情報がありませんので、基本的に経営状態に関しての要件を気にする必要はありません。
適切な場所かどうか
酒類販売業免許の取得で意外とハードルになるのが場所的要件です。
もっとも、輸出酒類卸売業免許を取得しようといった方の場合はしっかりと事業用オフィスを契約しているケースが多いため、契約書の提出や所有者の承諾書類の回収で問題ない場合が多くなっていますが、個人で取得を検討しようとされる方の中にはご自身が所有するマンションでの免許取得を目指した結果、マンションの管理組合等から承諾が得られないなどの問題がクリアできなケースがあるのでご注意ください。
免許が取得できる場所なのかどうかはしっかりと確認しておく必要があります。
輸出酒類卸売業免許の取得にあたっては酒類販売業の経験はなくてもいいが貿易等の実務経験等が求められる
酒類販売業免許取得にあたって、基本的に酒類の販売業経験が問われるのですが、輸出酒類卸売業免許では酒類販売の経験がなくても要件を満たすことは可能です。
したがって、お酒のビジネスをこれまでやってこなかった事業者(あるいは個人)が免許を取得し、輸出卸をするケースというのも少なからずあります。
ただ、適切な取引ができるということ自体は免許取得要件になっていますので、要件が緩くて簡単に取得できるというわけではありませんのでご注意ください。
貿易実務の経験・知識があるかどうかなど、酒類販売業以外のところの経験値から総合的に判断されることとなります。
基本的に輸出入に関する実務をやっている会社、あるいは個人が輸出酒類卸売業免許を申請する場合が多いかと思います。
補足として、酒類卸売業免許は基本的に酒類販売の実務経験が問われるため、輸出入酒類卸売業免許と合わせてその他の酒類卸売業免許の申請も検討されている場合はご注意ください。
また、個人の方の場合は経営経験(経営能力)があるのかどうかという点にも注意が必要です。
取引承諾書が必要
酒類販売業免許を取得してから取引先を探そうとお考えの方も稀にいらっしゃるのですが、酒類販売業免許の申請にあたっては取引先が定まっている必要があるため、免許が取れてから仕入先あるいは販売先を確保しようというお考えだと免許取得は困難であると言えます。
輸出酒類卸売業免許の申請にあたっては取引承諾書の提出が必須ということもありますので、取引先の開拓は免許申請前に行っておく必要があります。
なお、取引承諾書が英語(外国語)表記だけだと受付してもらえないので、英語だけでなく日本語を併記するようにしましょう。
通信販売(ECサイト)で海外へお酒を販売する場合も輸出酒類卸売業免許が必要なことに注意
ECサイトでお酒を販売するんだから通信販売酒類小売業免許だけで問題ないですよね?と聞かれることがあるのですが、海外へお酒を販売(輸出)するのであれば、輸出酒類卸売業免許が必要となります。
また、管轄の税務署によって判断がわかれる部分もありますが、輸出酒類卸売業免許に加えて通信販売酒類小売業免許も合わせて取得するように言われることもあるかと思います。そもそもECサイトの仕組みが海外のみならず日本国内でも販売可能である場合は通信販売酒類小売業免許も必要となりますので、そういった前提であれば間違いなく必要ですが、そうでないケースでも問われる場合はあるかと思います。
事業モデルを整理し、適切な免許を取得するようにしてください。
輸出時の酒税の取扱いやその他手続きを適切に行う
酒類販売業免許申請とは直接関係しませんが、お酒を輸出する際は酒税が免除されるケースがあります。
税務に関しては税理士への相談が必要ですが、輸出にあたって必要となる税務処理からその他手続きも含めて適切な対応が求められることにご注意ください。
参考:酒類の輸出免税等の手続について、日本酒輸出ハンドブック
輸出酒類卸売業免許取得にかかる費用
輸出酒類卸売業免許の取得にあたっては、公的資料の収集にかかる費用、登録免許税が主な費用となります。
公的資料の収集は数千円から1万円程度が目安となります。
登録免許税は9万円となります。
なお、行政書士への依頼も検討されているケースでは行政書士への報酬が15万円前後かかってきます。高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、手間の削減等も考慮すると決して損な価格帯ではないと個人的には考えます。
酒販免許申請の費用については以下の記事でも細かく解説しておりますので、費用面が気になる方はご参考ください。
お酒を輸出するなら一般消費者が対象であっても輸出酒類「卸売」業免許の取得が必要
通常、お酒を一般消費者へ販売する場合は酒類小売業免許が必要となりますが、輸出に関しては輸出酒類卸売業免許が必要となり、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許では販売できません。お酒の輸出ビジネスを検討している方はご注意ください。
なお、アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請の代行・サポートサービスを提供しております。
酒類卸売業免許の申請にあたり、細かい要件の確認や書類の作成などが求められますが、なかなか自分でやるのは厳しいといった方も多くいらっしゃいます。
酒類販売業免許は税務署への事前相談や申請中のやりとりを含めて意外と手間がかかりますので、行政書士への依頼もご検討いただければと思います。