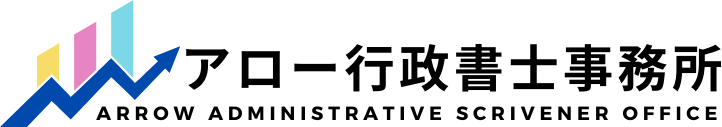インターネットを通じて消費者等へ商品を販売するビジネスモデルは極めて一般的なものとなっています。
当然お酒のビジネスもネットを活用したものが増えており、法人・個人問わず相談は多いでしょう。
特に個人の副業やサラリーマンの定年退職後のお酒に関わるスモールビジネスとして、お酒のインターネット販売(ECサイト等)を検討される方は少なくありません。
そこで、このページでは、ECサイトなどのインターネットを通じてお酒を一般消費者に向けて販売することを目的とした場合、どんな免許が必要か?免許を取得するにはどうすればいいか?といったことを解説していきます。
アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請の代行・サポートサービスを提供しております。
申請でお困りでしたらぜひご相談ください。
お酒の販売に関する免許の種類はたくさんある
はじめに、お酒の販売免許(酒類販売業免許)はどんなものがあるのかを理解する必要があります。
お酒を販売するための免許は大きく2つに分類でき、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つがあります。
「酒類小売業免許」は一般消費者や飲食店へ小売りする際に必要な免許です。
「酒類卸売業免許」は酒類業者等へ卸売りする際に必要となる免許となります。
ここではかなりザックリと説明させていただきましたが、一般消費者に向けてインターネットでお酒を売りたいと思ったら、大きな分類として酒類小売業免許が必要になるんだなということはなんとなくご理解いただけたかと思います。
※このページでは酒類卸売業免許の説明は省略させていただきます。業者向けに販売するから卸売業免許や他の免許が必要だなと感じた方は詳しくはお酒の販売免許の種類のページをご覧ください。
■簡易まとめ
お酒を販売する免許は、
・酒類小売業免許
・酒類卸売業免許
の2つに大きく分けられ、一般消費者向けの販売は「酒類小売業免許」が必要。
酒類小売業免許について
酒類小売業免許は、「一般酒類小売業免許」、「通信販売酒類小売業免許」、「特殊酒類小売業免許」の3つに分類できます。3つ目の特殊酒類小売業免許はほとんど今回の話には関係ないと考えられるため、今回は説明を省略させていただきます。
一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許はお酒の販売免許でもっともスタンダードなものであり、一般消費者や飲食店に向けてお酒を販売する際に必要となる免許となります。基本的にすべての種類のお酒が取り扱えます。
コンビニやスーパー、酒販店など、店舗を構えて一般消費者に販売するスタイルの他、店舗を持たずに事務所機能だけを有した飲食店向け専門にお酒を販売する業者もあります。
注意点としては、販売場のある都道府県のみ(1つの都道府県のみ)でしかお酒を販売できないということです。
店舗型であれば特に大きな問題にはなりませんが、飲食店向けにお酒を販売するケースでは注意が必要です。
なお、1つの都道府県のみでの販売であれば、インターネット等による通信販売も可能です。東京都だけ、神奈川県だけなど特定の都道府県のみでお酒のインターネット販売をするのであれば、一般酒類小売業免許です。
検討している販売方法・販売先等によって必要な免許を考えていく必要があります。
一般酒類小売業免許については以下のページもご参考ください。
通信販売酒類小売業免許(ネットでお酒を販売するならこれが必要)
インターネット等の通信販売による方法でお酒を販売していきたいと思った際は、通信販売酒類小売業免許が必要となります。
2都道府県以上にまたがって、インターネットやチラシ、カタログなどでお酒を販売するケースでは通販免許が必要となります。
先ほど説明した一般酒類小売業免許は1つの都道府県のみでしか販売ができませんでしたので、当該免許で複数都道府県で販売する予定がある場合はネット販売等によらない方法であったとしても通信販売酒類小売業免許を取得するように言われることがあります(地域や状況により判断が異なります)。
一般と通販の両方取得するケースも多いでしょう。
■酒類小売業免許について
・一般酒類小売業免許:1都道府県内で一般消費者や飲食店へ販売
・通信販売酒類小売業免許:2都道府県以上にまたがりネット販売等の通信販売により一般消費者等へ販売する場合に必要な免許
インターネットによるお酒の販売を考えているなら通信販売酒類小売業免許が必要
上記で記載したとおり、2都道府県以上にまたがってインターネット上でお酒を不特定多数の消費者向けに販売していこうと思った際は通信販売酒類小売業免許が必要となります。
※1都道府県限定であれば一般酒類小売業免許。
ただし、通信販売酒類小売業免許を取得すればネット上ですべてのお酒を売ることができるのかと言えばそうでもありません。
酒類販売業免許は、免許区分ごとにできること、できないことがあるので注意が必要です。
また、地域ごとで若干審査側の解釈異なるケースもあるので必ず税務署等に確認してから進めることをおすすめします。
通信販売酒類小売業免許で「できること」と「できないこと」を把握する
通信販売酒類小売業免許は販売可能なお酒の種類に制限があるなど一定の制約があるため注意が必要です。
大まかに要点を記載すると、輸入酒に関しては制限なく取り扱いが可能ですが、国産酒に関しては大手酒類製造事業者のお酒は基本的に販売ができません。
本当に自分がやりたいことができるのかしっかりと見極める必要があります。
詳しく見ていきましょう。
国産酒は課税移出数量3,000kl未満の酒類製造者のお酒しか販売できない
特に注意が必要なのが、販売可能なお酒の種類等に制限があることです。
国産酒であれば課税移出数量3,000kl未満の酒類製造事業者のお酒のみが販売可能となります。
品目ごとにすべて3,000kl未満である必要がありますので、大手の国産メーカーのお酒は基本的に販売できないとお考えください。
また、販売にあたっては品目ごとに3,000kl未満証明書の提出が必要です。
3,000kl証明書をメーカー等から出してもらう必要がある
酒販免許申請時には3,000kl未満の証明書が必要となります。
これを酒類製造業者等から発行してもらわなければなりません。
品目ごとに証明書が必要なので、多数の品目を製造している酒類製造者から3,000kl未満の証明書を取得することができれば、その他の製造者のものも当該品目については取扱い自体は可能です。
ただ、新しい酒類製造業者のお酒を取り扱おうと思った際に、そこが3,000kl未満かの確認は必要ですので、どちらにせよ3,000kl未満の証明書を取得し確認することが求められます。なお、この場合においては税務署への証明書の提出は不要です。
申請時に仕入先が決まっている必要があるということ
3,000kl未満の証明書を出してもらうにあたっては、ある程度関係性の構築が必要です。酒類業界は比較的古い体質であり、閉鎖的です。
申請にあたっては仕入先が1つは決まっている必要があるので、とりあえず先に酒販免許だけ取っておこうということはできません。どこから仕入れるのかまでしっかりと準備しておく必要がありますのでご注意ください。
大手のECサイトでは普通に大手のビール会社や酒造メーカーのお酒が販売されているけどなぜ?
大手のネットショップでは有名大手酒類製造メーカーの国産酒のお酒を取り扱っていると思うけどどうやっているの?と思う方もいるかもしれません。
実は昔の酒販免許は本ページで記載したような制限がなかったので、昭和(1989年以前)の酒販免許をお持ちの場合は大手の国産のお酒の販売ができているという状況です。ゾンビ免許なんて言ったりします。
なので昔の酒販免許を持っている方はこうしたことも可能なのですが、これから新規で取得する方は制限があるため、基本的に大手のお酒の販売は難しいとお考えください。
地方の特産品を原料とする酒類は例外がある
地方の特産品等を原料として酒類を製造する場合においては、課税移出数量3,000kl以上の種類製造事業者が製造するものであっても、製造数量が年間3,000kl未満であれば通信販売が可能な酒類の対象となります。ただ、これに該当する申請はほとんどみたことがありません。
輸入酒の販売は特に制限なくできる
国産ではなく輸入酒であれば特にお酒の販売品目に制限はありません。
ただし、事業者として輸入品を販売するためのルールは守る必要があるため、そういったものについてはご自身でしっかりと勉強する必要があるためご注意ください。
インターネットで販売できるお酒には制限があるためご注意ください。なお、一般消費者へ販売するだけであれば、輸入するにあたり、輸入酒類卸売業免許は必要ありません。
ネット通販で海外向けにお酒を販売するなら輸出酒類卸売業免許が必要
近年は越境ECなどで海外へお酒を販売するケースも増えているかと思います。
このあたりのルールは年々変更となってきているのですが、現状は輸出酒類卸売業免許の取得が必要であるということになっています。
税務署によっては輸出酒類卸売業免許に加えて通信販売酒類小売業免許の取得を促されるケースもあるでしょう。
なお、海外限定で販売するためのECサイトではなく、日本国内でも海外でも購入できるサイトなのであれば、両方の免許が必要になるかと思います。
輸出酒類卸売業免許については以下ページをご参考ください。
通信販売酒類小売業免許の取得要件について
基本的には一般酒類小売業免許と同じ要件なのですが、通信販売酒類小売業免許は他の酒販免許と比べると求められる要件自体は低く、比較的取りやすい免許です。
要件については細かくて記載しきれないため、大枠をご案内します。
人的要件
申請する方や役員が税金等を滞納していたり、過去にお酒に関する罰則等を受けていないことが必要です。
意外とあるのが納税証明書を取得する際に未納であることが発覚することがあるのでご注意いただきたい事項となります。
申請先が税務署なので、税については注意が必要です。
経営基礎要件
直近決算の貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合や直近3事業年度連続で資本等の額の20%を超える赤字を出している場合は酒販免許が受けられません。会社の経営状態が健全であることが求められます。意外と該当するケースがあるため、決算数字には注意が必要です。
直近で大きな赤字を出している、3期連続でそこそこの赤字が続いているという場合は注意が必要です。
また、可能な限り酒類販売に関する経験や経営経験があることが求められます。
通信販売免許の場合はそこまで厳しく求められないので、過去の経験やお持ちの資格から満たせるケースが多くなっています。うまくご経験を棚卸し、書類を作っていくことでクリアができるケースもあるので、若い人でも経営経験があると判断できることもあるでしょう。
お酒の業務経験については、酒類販売管理者研修の受講等その他でクリアできるケースも多くなっています。
場所的要件
酒販免許で一番大変なのが、場所に関する要件だなと個人的には感じています。
特にインターネット販売で副業的に酒類販売を行おうと思っている方の場合、お住いのマンション等で免許を取得したいとお考えになるケースも多いのですが、管理組合の承諾が得られず断念せざるを得ないケースが多くなっています。
また、マンションがダメならレンタルオフィスで、、、と考える方も多いのですが、個室である必要があるのはもちろんのこと、ビルそのものの所有者の承諾書あるいは所有者と運営会社側との賃貸契約書の開示を税務署が求めてくるので、なかなかハードルが高く、うまくいかないケースが多くなっています。原契約がどうなっているのかを見てくるわけです。
レンタルオフィスを借りる前に、細かい部分を確認する必要があるためご注意ください。
なお、レンタルオフィスで免許を取ることが不可能なわけではありません。ただ、上記で記載したように、レンタルオフィス側もそれは無理、と断ってくるケースがあるためご注意ください。
場所的要件はこれら以外にもいろいろあるため、内装工事等含めて大きく手を入れる前にしっかりと免許が取れる場所なのかは確認が必要です。
需給調整要件
ザックリ記載すると、どの品目のお酒を、どこから仕入れて、どのように、どこで売るのか?お酒の販売の流れを示すこととなります。
ここまでで記載したとおり、国産酒に関しては制限があることを説明させていただきました。
適切な仕入先の確保等が求められます。
通信販売酒類小売業免許申請の必要書類
状況によって変わってくる部分はありますが、以下のような書類が必要となります。
【必要書類例】
申請書、次葉1~6(販売場敷地状況、建物等配置図、事業概要、収支見込表、資金、酒類販売管理取組計画書)、誓約書、履歴書、地方税納税証明書、財務諸表(3年分)、土地建物登記事項証明書、定款の写し、賃貸借契約書・所有者の承諾書、ECサイト概要
等
申請者が法人なのか個人事業主なのか、新設法人なのかなどにもよって変わってきますが、上記のような書類が必要です。
お酒を販売するECサイト等の概要が求められる
酒販免許の手引きの最後の方に記載されていますが、申請書の作成にあたり、お酒を販売するサイトの構成等を記載したものを添付する必要があります。
特定商取引法に基づく表記等を含め、買い物カゴや自動返信メールの文言など細かいものを提出する必要があります。
実際の完成形である必要はありませんが、お酒をネット販売するにあたって必要なことが理解できているかが重要となります。
デザイン等が求められているわけではなく、表示させる要素が提示できれば問題ないこととなります。
法律で定められた要件を理解しているかどうかなどが見られていることとなります。
なお、アロー行政書士事務所では申請で使用するECサイトのサンプルの作成ももちろんすべて行っておりますのでご安心ください。
通信販売酒類小売業免許申請にかかる費用
通信販売酒類小売業免許にかかる費用は、概ね以下のようになります。
自分で申請するなら4~5万円程度
登録免許税3万円、役所等から取り寄せる資料にかかる費用5千円~1万円程度(状況により大きく変動することがあります)。
行政書士に依頼するなら15~20万円程度
酒類販売業免許は行政書士に申請を依頼するケースも多いかと思いますが、行政書士への報酬が概ね10~15万円程度かかってきます。
そのため、登録免許税と諸経費を合わせると15~20万円程度はかかってくることが予想されます。
どの程度費用がかかってくるかは各人のご状況によるところもありますのであくまでも参考としてご覧ください。
費用については以下のページで詳しく解説しています。
副業の場合はネット販売がほとんどなので通信販売酒類小売業免許の取得を目指すケースが多い
近年は副業でお酒の販売を始めたいというケースもありますが、このようなケースでは、ビジネスモデルという点はもちろんですが、免許要件を満たせるかという意味でも通信販売酒類小売業免許の取得を目指すケースが多くなっています。
副業で通販免許の取得を検討している場合は以下の記事もご参考ください。
ECサイトを含めてネット販売するためのHP等は免許申請前にできている必要はない
通信販売酒類小売業免許の申請にあたり、事前にECサイト等が完成している必要はありません。
申請時にECサイト等の見本を添付する必要はありますが、サイト自体は完成している必要はなく、また、免許取得後に関してもそもそも申請した際に提出したものと違う内容のサイトになっていても問題ありません。
そもそもネット環境は時代の流れによっても大きく変わってくるので、デザインからサイト構成まで含めて頻繁に変わるものでもあります。申請にあたってはあくまで法的に必要な機能や要件が備えられているサイトなのか(理解しているか)などがチェックの対象となります。
申請先は管轄の税務署だが相談については酒類指導官がいる税務署となるため注意
酒類販売業免許の申請先は税務署となります。相談先も税務署です。
ただ、申請にあたっての相談は酒類指導官のいる税務署への相談が必要であり、申請先の税務署とは異なる場合がありますのでご注意ください。
お住いのエリア(営業場所)によるところがございます。
税務署とのやりとりも多くなりますが、相談の結果、税務署から免許取得は無理では?といわれてしまうケースもあるためしっかりと準備してから臨むことをおすすめします。
また、行政書士の活用もご検討ください。
インターネットでお酒を販売するなら通信販売酒類小売業免許の取得を目指す
本ページで記載したように、お酒のネット販売ビジネスをする予定があるのであれば通信販売酒類小売業免許の取得を目指しましょう。
なお、海外へお酒の販売をしようとお考えの場合は輸出酒類卸売業免許が必要となりますのでご注意ください。
以下の表は通信販売酒類小売業免許の概要をまとめたものです。
| 免許名 | 販売形態 | 販売可能なお酒の種類 |
|---|---|---|
| 通信販売酒類小売業免許 | ・インターネット販売 ・カタログ販売 ・チラシ販売 | ・輸入酒はすべて販売可 ・国産酒は課税移出数量3,000kl未満(特産品等は製造委託数量合計3,000kl未満) ※大手の国産メーカーのお酒の販売は難しいということになります。 |
本業の事業展開としてネットを使ってお酒の販売ということももちろんあるのですが、副業や定年退職後のサイドビジネス的な感覚でお酒の通信販売をやりたいということで通販免許取得を目指されるケースが増えているように思います。
特に副業や定年退職後の新たなキャリアという視点で酒販免許を目指すケースでは、酒販免許を甘く見ているケースも非常に多くなっており、お酒の知識がそれほどないという方はもちろんのこと、仕入先の目星すらついていないというケースも珍しくありません。
そういったケースでは、免許申請どころではないので、まずはしっかりと仕入先を調べ、あたってみることからしていただく必要があるでしょう。
通信販売酒類小売業免許申請はアロー行政書士事務所へご相談ください
仮に仕入先等の開拓を含めた準備をしっかりと済ませ、要件を満たしていたとしても、酒販免許は申請書や添付書類の作成が非常に細かく手間がかかり、複雑です。
申請書に添付するネット販売用のサイト概要の資料作成もなかなか大変です。
アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請の代行・サポートサービスを提供しておりますので、書類作成部分も含めて申請でお困りのケースがあればぜひご相談いただければと思います。
自分はそもそも要件を満たしているのか不安だという方は要件の相談からもちろん可能ですので気軽にお問い合せください。
インターネットでのお酒の販売を含め、酒販免許申請でお困りでしたらぜひご相談ください。