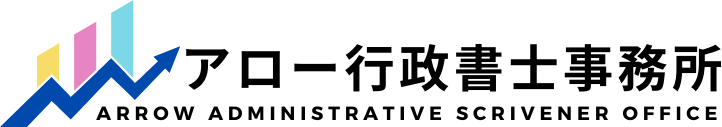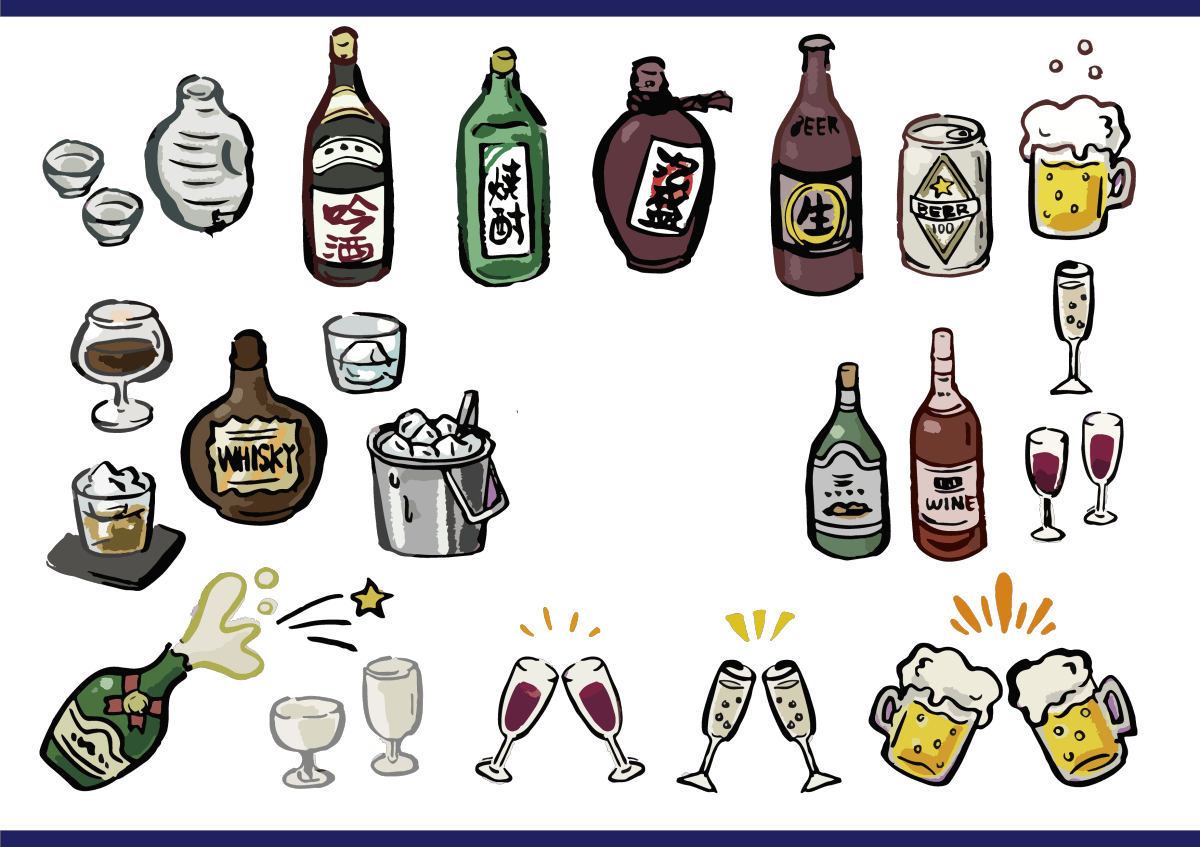酒類販売業を検討している方にとって、避けて通れない知識の1つとして「酒税法における酒類の分類」があるでしょう。
申請にあたっても酒類販売業免許取得時に品目が指定されたり、免許区分によっては取り扱うこのできる酒類の品目に制限があったりします。
取り扱う酒類に応じて適切に申請書に記載していかなければなりませんので、税法上の酒類がどのように分類されているのかをある程度把握しておくことは重要だと言えるでしょう。
本ページでは、酒税法の17品目という分類の全体像から、身近なお酒がどの品目に該当するかの紹介をしていきます。
なお、国税庁酒税法における酒類の分類及び定義より引用して記載をしております。
※法改正等があった際に当ページの更新がリアルタイムで間に合わない場合がございますがご了承ください。
酒類の分類・定義について
酒税法による酒類の分類は課税上の分類として製造方法における4つと酒類の品目として17種に分類されています。
製造方法等による酒類の分類
酒類は発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4つに分類されます。
発泡性酒類
ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分が11度未満(※)で発泡性を有するもの)
(※)令和8年9月30日までは10度未満
醸造酒類
清酒、果実酒、その他の醸造酒。
※その他の発泡性酒類に該当するものは除かれます。
蒸留酒類
連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ。
※その他の発泡性酒類に該当するものは除かれます。
混成酒類
合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒
※その他の発泡性酒類に該当するものは除かれます。
酒類の品目
以下は国税庁の資料を抜粋した種類の品目となります。
各品目の具体例はわかりやすさを重視しておりますので厳密ではありませんが、ご参考ください。
| 品目 | 定義の概要と例 |
|---|---|
| 清酒 | ・米、米こうじ及び水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの) ・米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの) ※具体例としては、日本酒のことです。 |
| 合成清酒 | ・アルコール、焼酎又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの) ※具体例としては、日本酒風味のアルコール飲料となります。 |
| 連続式蒸留焼酎 | ・アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が36度未満のもの) ※無色透明で原料を感じない焼酎がわかりやすい例であり、例えばチューハイのベースで使われる焼酎、ホワイトリカーなどがあるでしょう。 |
単式蒸留焼酎 | ・アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が45度以下のもの) ※いわゆる芋焼酎や麦焼酎等と呼ばれているものはこれに入るかと思います。 |
| みりん | ・米、米こうじに焼酎又はアルコールを加えてこしたもの(アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの) ※文字通りみりんがわかりやすい例でしょう。なお、みりん風調味料は酒類ではありません。 |
| ビール | ・麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの) ・麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもので、下記の条件を満たすもの(アルコール分が20度未満のもの) ・上記に掲げるビールにホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもので、下記の条件を満たすもの(アルコール分が20度未満のもの) (条件)麦芽比率が100分の50以上であること並びに使用した果実(乾燥したもの、煮詰めたもの又は濃縮した果汁を含む。)及び一定の香味料の重量が麦芽の重量の100分の5を超えない(使用していないものを含む。)こと ※いわゆるビールです。 |
| 果実酒 | ・果実を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの) ・果実に糖類を加えて発酵させたもの(アルコール分が15度未満のもの) ・上記に掲げる果実酒にオーク(チップ状又は小片状のもの)を浸してその成分を浸出させたもの ※ワインが代表的な例でしょう。 |
| 甘味果実酒 | ・果実酒に糖類又はブランデー等を混和したもの ※ベルモット、シェリーなどがその例となります。 |
| ウイスキー | ・発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの ※これは文字通りとなります。スコッチ、アメリカン、カナディアン、アイリッシュ、ジャパニーズなど。 |
| ブランデー | ・果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの ・果実酒にオーク(チップ状又は小片状のもの)を浸してその成分を侵出させたものを蒸留したもの ※コニャックがわかりやすい例でしょうか。ウイスキーに似ていますが果物を原料としているので原料としてはワインと似たものがあります。 |
| 原料用アルコール | ・アルコール含有物を蒸留したもの(アルコール分が45度を超えるもの) |
| 発泡酒 | ・麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの) ・ホップ又は苦味料を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの) ・香味、色沢その他の性状がビールに類似する酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの) ※ビールに似ていますがビールとして認められない原料を使用しているものが発泡酒となります。 |
| その他の醸造酒 | ・穀類、糖類等を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上のもの) ※どぶろく等 |
| スピリッツ | ・上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの ※四大スピリッツとよばれるジン、ウォッカ、ラム、テキーラがわかりやすい例でしょう。 |
| リキュール | ・酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの ※梅酒、杏酒、カンパリ、キュラソーといったものが一例となります。 |
| 粉末酒 | ・溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの |
| 雑酒 | ・上記のいずれにも該当しない酒類 |
酒類販売業免許申請の際も品目が指定される場合がある
一般酒類小売業免許のようにすべての酒類が取り扱える免許ばかりでなく、指定された品目の酒類の販売が可能な免許もあります。
通信販売酒類小売業免許や洋酒卸売業免許などのように、指定された品目のみが扱えるという場合もあります。そのため、免許申請時点においても、ある程度酒類の品目は理解しておく必要があるでしょう。
※洋酒卸売業免許は洋酒にカテゴライズされるお酒はすべて指定されるケースが増えています。
酒類販売業免許申請でお困りならご相談ください
このページでは酒類の品目について簡単に解説させていただきました。
閲覧者の中には酒類販売業免許の取得を検討されている方もいらっしゃるかと思いますが、もし酒販免許申請でお困りでしたらご相談ください。
アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請代行・サポートサービスを提供しておりますので、お困りの方は当該ページもご覧いただければと思います。