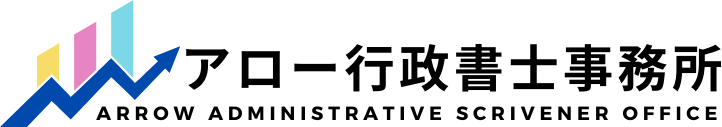海外からワインを輸入して販売したい!海外のビールを輸入して販売したい!など、海外からお酒を輸入して販売したいという相談は一定数ございます。
お酒を輸入する免許で代表的なものは輸入酒類卸売業免許(税務署の手引きには輸出入酒類卸売業免許と記載がありますが輸出と輸入は別の免許です)となりますが、仕入れるお酒の品目や販売先によって必要となる免許は変わってきます。
このページでは、お酒を輸入して販売したい!という方向けに酒類販売業免許について解説していきます。
アロー行政書士事務所ではお酒を輸入して販売したいとお考えの方向けの酒販免許申請の代行・サポートサービスを提供しています。
免許申請でお困りでしたらぜひご相談ください。
輸入したお酒を誰にどのように売るのかで必要な酒類販売業免許が異なる
お酒を輸入して販売する場合に必要となる免許で最初に思い浮かぶのが「輸入酒類卸売業免許」かと思います。
ただ、「卸売業免許」という記載からわかるとおり、お酒を輸入して「卸売」する場合に必要となる免許となります。
したがって、この免許は、お酒を輸入して同じ酒類卸売業者や酒屋、スーパーマーケット、コンビニなどの酒販店(酒類販売業者)へ卸売する場合に必要となる免許となります。こうした場合は輸入酒類卸売業免許などの卸売業免許が必要となります。
一方で、輸入したお酒を一般消費者や飲食店等に小売するのであれば、一般酒類小売業免許のように小売業免許が必要となります。卸売業免許では一般消費者へ販売できません。
お酒を輸入して販売したいといっても販売先等によって必要な免許が異なりますので、どこから輸入し、誰に対して、どんなお酒をどのように販売するのかをまずは整理しましょう。
小売業免許と卸売業免許の違いなどの基本的なことや各種免許の違いについて知りたい方は以下の記事をご参考ください。
輸入したお酒を販売するのに必要な免許をパターン別に紹介
上記で記載したように、お酒をどこから仕入れ、誰に、どのように販売するのかによって必要な免許は変わってきます。複数の免許が必要な場合もあるでしょう。
よくあるパターンを例に必要となる免許を見ていきましょう。
なお、細かく厳密に見ていくともっといろいろなパターンがある他、細かい注意点もございます。
置かれた状況等によって変わってくる部分もございますので、あくまで1つの参考例としてご覧いただければと思います。
輸入したお酒を自分のお店・店舗やネットで一般消費者に販売する場合は一般酒類小売業免許あるいは通信販売酒類小売業免許が必要
よくあるパターンとしては、お酒を輸入して自分のお店で一般消費者向けに販売したいというケースです。
この場合であれば一般酒類小売業免許が必要です。
また、ネット通販で販売するということであれば通信販売酒類小売業免許が必要です。
なお、輸入したお酒を自分のお店やネットで消費者などの小売業免許で販売できる対象向けに販売するだけであれば輸入酒類卸売業免許はなくても大丈夫です。
飲食店向け(飲食用)の配達も小売に該当しますので、飲食店専門にお酒を配達販売しているようなケースでも小売業免許が該当します。
それぞれの免許については以下のページをご参考ください。
お酒を輸入して酒屋やスーパー等の他の酒販免許業者等に卸売するなら輸入酒類卸売業免許が必要
輸入酒類卸売業免許が必要となるのは自社でお酒を輸入して卸売をする場合となります。
つまり、輸入したお酒を他の酒類販売業者へ販売する場合に必要となるということです。上記で記載したように自分のお店等で一般消費者に販売するだけであれば輸入酒類卸売業免許はなくても大丈夫です。
輸入酒類卸売業免許は品目を問いませんのですべてのお酒を輸入することができます(指定された品目であれば)。
なお、洋酒卸売業免許を取得している場合であれば、洋酒卸売業免許で指定されている品目であれば輸入して卸売することも可能です。
他社が輸入したお酒を仕入れて卸売するなら洋酒卸売業免許などのその他の該当する卸売業免許が必要
上記で記載したように、輸入酒類卸売業免許はあくまで自社(自己)が輸入する際に必要となる免許となりますので、他社が輸入した海外のお酒を仕入れて卸売するというケースでは別途該当する免許を取得しましょう。
輸入というケースにおいてはワインなどの果実酒を仕入れて卸売したいという場合が多いので、洋酒卸売業免許を取得するケースが多いでしょう。
洋酒卸売業免許については以下をご参考ください。
その他各種免許の種類については以下のページをご参考ください。
輸入酒類卸売業免許が絶対に必要というわけではない
お酒を輸入して販売しようと思っている方の中には輸入酒類卸売業免許が必要だと思っている方が多いのですが、必ずしもそうではありません。
先ほど記載したように、お酒をどこから仕入れて、誰に対して、どのように売るのかによって必要な免許が異なってきます。
輸入酒類卸売業免許でできること、できないこと、他の免許でできること、できないことはある程度把握するようにしておきましょう。
なお、冒頭にも記載しましたが、税務署の手引きには輸出入酒類卸売業免許と1つの免許であるかのように記載されていますが、輸出と輸入はそれぞれ別の免許であり、「輸入酒類卸売業免許」と「輸出酒類卸売業免許」とわかれていますのでご注意ください。
以下、お酒を輸入するという側面でみた場合の各免許区分の説明図。
| 販売シナリオ | 仕入れ方法 | 販売先 | 販売方法 | 必要な免許 |
|---|---|---|---|---|
| 自社輸入→店舗販売 | 自社で輸入 | 一般消費者 | 店舗での対面販売 | 一般酒類小売業免許 |
| 自社輸入→ネット販売 | 自社で輸入 | 一般消費者 | インターネット通販 | 通信販売酒類小売業免許 |
| 自社輸入→飲食店配達 | 自社で輸入 | 飲食店(飲食用) | 配達販売 | 一般酒類小売業免許(場合によっては通販免許も) |
| 自社輸入→業者卸売 | 自社で輸入 | 酒屋・スーパー等 | 卸売 | 輸入酒類卸売業免許 |
| 他社輸入品→業者卸売 | 他社輸入品を仕入れ | 酒屋・スーパー等 | 卸売 | 洋酒卸売業免許等の卸売業免許 |
| 複合パターン | 自社で輸入 | 消費者+業者双方に販売等 | 店舗+卸売 | 一般酒類小売業免許、輸入酒類卸売業免許 |
輸入酒類卸売業免許について
輸入酒類卸売業免許についても説明しておきたいと思います。
輸入酒類卸売業免許は、自社(自己)が輸入する酒類を卸売できる酒類卸売業免許です(手引きより)。
ここまでで説明したように、あくまで自分が輸入する場合に必要な免許であり、また、卸売に該当する場合に必要な免許です。
また、取り扱える酒類の品目に制限はなく、指定された品目であればすべて取り扱いが可能です。
免許申請にあたっては仕入先・販売先の取引承諾書が必要
輸入酒類卸売業免許を取得しようとする方の中には、免許が取得できてから仕入先や販売先を探そうと思っている方もいるのですが、それでは免許は取得できません。
販売先・仕入先に関して、最低でも1つは当てがないと申請ができません。
実際の申請時には取引承諾書等が求められますのでご注意ください。なお、承諾書は英語(外国語)表記のみだと審査できないため、英語(外国語)に加えて日本語を表記して承諾書を得るようにしましょう。
酒類販売経験がなくても要件を満たせるケースが多い
税務署によって判断が異なる可能性はありますが、酒類販売業の経験がなくても免許自体は取得可能なケースが多くなっています。
ただ、輸入などの貿易実務ができるのか?等も見られる可能性があるのでご注意ください。
酒販免許以外の酒類の輸入手続きも当然必要
輸入酒類卸売業免許を取得しようという事業者様の大半が何かしらの貿易実務(輸出入)を行っているケースが大半なので問題ないとは思いますが、酒類販売業免許の他に輸出入に伴い検疫所・税関手続きが必要となります。
酒類販売業免許は税務署が管轄となりますが、食品等輸入届出などの手続きは税関となります。
お酒を輸入して販売するにあたって必要となるその他の義務にもご注意ください。
お酒を輸入して販売するための酒類販売業免許申請でお困りならアロー行政書士事務所にご相談ください
このページではお酒を輸入して販売するにあたって必要となる免許は、誰に対してどのようにお酒を販売するのかで異なることを説明させていただきました。
複数の免許が必要となるケースも多くございますが、いずれにせよ、まずは商流を整理する必要があるかと思います。
そうした整理から免許申請・免許取得までしっかりとサポートさせていただきますので、酒類販売業免許取得でお困りでしたらぜひご相談ください。
酒類販売業免許申請代行・サポートサービスページにサービスの特徴等も記載しておりますので、今日もがございましたらそちらのページもご覧ください。