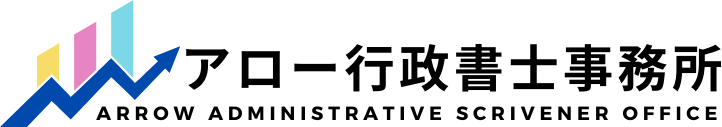このページでは酒類販売業免許申請で必要となる書類について解説していきます。
なお、酒類販売業免許申請といってもさまざまな免許区分がある他、申請内容やご状況によりここには記載していない書類が必要となるケースもございますがご了承ください。
必要書類も含め、申請でお困りでしたらアロー行政書士事務所の酒類販売業免許申請サポート・代行サービスの利用もご検討ください。
酒類販売業免許申請で必要となる書類の一覧
はじめに、一覧で必要書類を見てみましょう。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 申請書 | |
| 次葉1~6とチェック表 | 販売場敷地の概要、建物配置図、事業の概要、収支見込、所有資金、酒類の販売管理の方法(酒類小売業免許の場合) 次葉1~6の書類と書類があるかどうかのチェック表 |
| 免許要件誓約書 | 納税をちゃんとしているか等を誓約する書類 |
| 定款の写し | 法人で申請する場合にのみ必要 |
| 経歴書 | これまでの役員全員分の経歴書の提出が必要で意外と重要です |
| 地方税の納税証明書 | |
| 直近3年間の財務諸表 | 法人で申請する場合にのみ必要 |
| 直近3年間の収支計算書(確定申告書等) | 個人で申請する場合にのみ必要だが、確定申告をちゃんとやっているなら基本的に省略可 |
| 土地と建物の登記事項証明書 | 販売場の土地と建物の全部事項証明書 複数の土地にまたがる場合はすべての土地のものが必要 |
| 賃貸借契約書の写し・承諾書 | 契約内容によっては不可な場合があるため承諾書等と合わせて必要となるケースが多い |
| 取引承諾書・3,000kl未満証明書等 | 卸売業免許の申請・通信販売酒類小売業免許申請で必要 |
| ECサイト等の概要 | 通信販売酒類小売業免許の申請で必要な書類でサイトの概要から特定商取引法に関する事項等 |
| その他書類 | 一例として飲食店が酒販免許申請する場合は状況に応じてレシートや納品伝票見本、区分表などが求められます。 また、自己商標卸売業免許の申請の際は契約書や企画書の提出が求められます。 |
上記が主な必要書類です。
続いて、それぞれの書類について解説していきます。
申請書
これは読んで字のごとく申請書そのものです。
国税庁のサイトからダウンロードが可能です。
申請書の他、次葉1~6のフォーマットもダウンロードが可能です。
入力にあたっては、地番と住居表記が求められますので記載の仕方にご注意ください。
なお、複数の土地にまたがる場合はすべての地番が必要です。
次葉の1~6の書類
こちらもひな形は国税庁のサイトからダウンロードが可能です。
次葉1:販売場敷地の状況
販売場の所在地がどこなのかを地図上で示す書類となります。
なお、販売場所在地を地番で記載する必要があるのでご注意ください。
次葉2:建物等の配置図(建物の構造を示す図面)
建物の間取り図のようなものです。
どの部屋で免許を取得し、どこに机や椅子があるのか、酒類販売管理者の標識掲示場所はどこなのか、陳列場所はどこなのか、といったことを図面に記載していきます。
オフィスや店舗の賃貸であれば図面があるはずなので、それに書き入れていけばOKです。
もしない場合は極端なことを言えば手書きでも大丈夫です。
細かい測量等はしていなくても大丈夫です。
次葉3:事業の概要(販売設備状況所)
これはフォーマットに従って記入するだけで大丈夫な資料です。
敷地は借地なのか自己所有なのかなどを選択し、広さ等を記入していきます。
数字さえわかれば特に難しい入力項目はないでしょう。
次葉4:収支見込(兼事業の概要付表)
これもフォーマットに従って記入していくこととなります。
注意点は、仕入先・販売先を記載する必要があるため、免許区分に応じて、取引承諾書や3,000KL証明書の取得を忘れずに行ってください。また、免許区分ごとに適切な仕入先かどうか(卸売業者なのか製造者なのか等)はチェックされますので、仕入先あるいは販売先が保有する免許区分が適切かどうかは確認ください。
小売業免許の場合においては販売先は一般消費者かと思いますので、一般消費者との記載で大丈夫です。ただ、飲食店向けの販売であれば具体的な飲食店名等を記載する必要があります。
また、どのぐらい仕入れをし、どのぐらい販売をし、どのぐらい利益がでるのかといったことを記入しなければならないので、ある程度年間の事業計画を練って記載する必要はあります。論理が破綻した計画書を提出される方も一定数いらっしゃいますが、明らかにおかしな数字が記載されていると指摘が入りますのでご注意ください。
なお、実際に事業を開始した後、記入した数字とかけ離れた結果になっても特に罰則等はないのでご安心ください。あくまで予定・計画です。
次葉5:所有資金の額・調達方法
これもフォーマットに従って記入していくものとなります。
酒類販売業免許申請では具体的に●円ないと免許が取得できないといったような金額要件は記載されておりませんが、適正に事業が営めるか、継続可能かどうかは審査されますので、事業資金がいくらあるのかは意外と重要です。
たとえば、10万円しか事業資金がないという状況で、お酒の仕入れ、賃貸オフィスを借りる、業務用冷蔵ケースを購入してお酒の管理をするといったことができるかというとほぼ不可能でしょう。仮にすべて既存の設備を使用し、費用が掛からずにできるとしてもあまりに少ない事業資金の場合は注意が必要です。
そのため、ある程度の事業資金を記載する必要があります。あるいは、事業資金は現在10万円しかないけど資金調達が確定していて100万円で事業を始めることができる、という状況なのであればそれを記載し、申請することとなります。
なお、調達というのは、基本的に融資になるかと思いますので、酒類販売業免許取得にあたり、確実に融資が受けられるということを証明する必要があります。
次葉6:酒類の販売管理の方法に関する取組計画書
これもフォーマットに従って記載していくこととなります。なお、酒類小売業免許の申請時に添付するものであり、卸売業免許では不要です。
酒類販売管理者選任予定者を記載することとなりますが、酒類販売管理研修の受講を忘れないようにご注意ください。
申請書チェック表
これもフォーマットが用意されているため、記載の内容をチェックしていくだけとなります。
注意点は、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許とでチェック表の中身が異なりますのでご注意ください。免許区分ごとで仕様が異なります。
免許要件誓約書
こちらもフォーマットに記載していくだけとなります。
なお、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許とで誓約書の中身が異なるためご注意ください。
定款の写し
法人で申請する場合は定款の写しが必要です。
事業目的に酒類販売に関する事項が記載されている必要があるため、変更が必要です。定款等の目的変更についてはご自身で行うか、司法書士へ依頼する必要があります。
経歴書
役員全員分(個人事業主であれば個人)の経歴書が必要です。
この経歴書は意外と重要です。
経営経験や酒類販売に関する経験の有無が審査要件となっておりますので、この経歴書から経験が伝わるようにする必要があります。
経歴書は記載のポイントがありますので、アロー行政書士事務所にご依頼いただく場合は独自のフォーマットをお渡ししております。
地方税の納税証明書
申請者の地方税納税証明書が必要です。
具体的には、都道府県税の納税証明書、市区町村税の納税証明書となります。
過去2年間において国税・地方税の滞納をしていないことを示すために必要な書類となります。
なお、申請先が税務署なので、国税に関しては税務署側で把握が可能なので特に書類の提出は不要です。地方税に関しては管轄が異なるので地方税の納税証明書が必要であるということになります。
なお、未納があればすぐに納付してもらえれば問題ありませんが、滞納がある場合は申請自体ができない場合があるためご注意ください。
納税証明書は地域によってやや内容が異なるので、酒類販売業免許申請で必要となる旨を役所側に伝え、必要なもの(過去2年の滞納処分と未納がないかがわかるもの)を取得するようにしてください。
直近3年間の財務諸表(個人の場合は確定申告書※収支報告書等)
申請にあたっては財務諸表の提出が必要です。ここでいう財務諸表とは、貸借対照表と損益計算書です。
3期分の決算をしていればあるはずですので、わからなければ税理士確認するようにしてください。
なお、新設法人の場合は3年間分の財務諸表の提出は求められません。
また、設立してまだ1期しか経っていない法人の場合は該当期分の財務諸表の提出で問題ありません。
3期分必要な理由は要件を満たしているかの確認が必要だからということになりますので、決算要件がクリアできているかは事前に確認してください。
個人の場合は確定申告書の提出で大丈夫です。決算要件等はないので、基本的には提出すれば問題ありません。
土地と建物の登記事項証明書
酒類販売場の土地と建物の登記事項証明書が必要です。
登記事項証明書を発行するには地番情報が必要なのでまずは地番を調べてください。
また、建物が複数の土地にまたがる場合はすべての土地の登記事項証明書が必要となります。
納税証明書よりは楽に取得ができるでしょう。
賃貸借契約書の写しや承諾書
基本的にオフィスや店舗を借りてお酒の販売をされるかと思いますので、その際の賃貸借契約書等が必要となります。
なぜ賃貸借契約書の写しを提出するのかというと、使用権がきちんとあるのかを確認するほか、賃貸の使用目的で酒類の販売をすることが記載されているかの確認となります。
また、賃貸人と所有者が違う場合においては、所有者がちゃんと酒類販売で使用することに承諾しているのか?の確認が必要となるケースがあるため、別途承諾書が求められるケースが多いです。
この他にもいろんなパターンがありますが、意外とこの賃貸物件の契約内容等がネックとなって申請が進まないケースはあるため注意が必要です。
取引承諾書・3,000kl未満証明書等
酒類卸売業免許の申請にあたっては、仕入先・販売先の取引承諾書の提出が必要です。取引先が海外の場合、英文等の外国語だけでなく、日本語の併記が必要なことにもご注意ください。
また、通信販売酒類小売業免許の申請にあたっては3,000kl証明書の提出が必要です(国産酒を取り扱う場合)。
ECサイト等の概要
通信販売酒類小売業免許の申請にあたっては販売するサイトの概要の提出が求められます。
具体的には、どのようなECサイトなのかといったサイトの構成や概要、特定商取引法に基づく表記、注文ページ、注文確認ページ、メール文・確認メール文等、納品書等の見本の提出が必要です。
これらの作成・提出にあたり、実際に稼働するサイトを事前に作成し、デザイン案等をフィックスさせておく必要はありません。あくまで概要の提出であり、また、確認事項としては法令に則ったサイトが運営できるのか?その知識があるのか等の確認となるので、実際に完成したサイトが提出したものと違っていても問題ありません。
なかなかご自身で作成するのは難しい場合が多いかと思いますが、要点をおさえて作成できればそれほど難しいものではありません。
その他
酒類販売ビジネスと一口にいってもその形態はさまざまですので、事業内容によっては追加で求められるものもございます。
たとえば、飲食店が酒類販売業免許を取得するにあたっては、飲食業と酒販事業がしっかりと区分されていることを証明するための資料の提出が求められます。レジ機能の分類やお酒の保管の分類、納品伝票の分類等となりますが、これらがしっかりできていることを示す必要があり、意外と書類は多くなります。
また、最近相談が増えている自己商標酒類卸売業免許申請にあたっては、OEMでお酒の販売をするにあたっての製造者との契約書や自己が開発したものであることを証明するための資料として商品企画書等の提出が求められます。
申請後も追加資料が求められることは多いので、しっかりと対応するようにしてください。
酒類販売業免許申請では場所に関する必要書類で苦戦する傾向にある
公的書類の収集や申請書・次葉書類は時間をかければなんとか作成できる場合が多いかと思います。
ただ、賃貸借契約書や建物所有者等からの承諾書はご自身の努力ではどうにもならないケースもあるため、なかなか大変な思いをすることも多いです。
大きな法人で初めから酒類販売用にオフィスを借りているケースでは問題ない場合が多いのですが、個人の副業やスモールビジネスとして小規模で始めたいという場合は自宅の賃貸や所有するマンション、レンタルオフィスでの免許取得を目指すケースが結構多くあり、その場合はかなり苦戦します。
マンションの場合は大家や管理組合からの承諾が必要となるので、なかなかうまくいかない場合が多くなっています。レンタルオフィスも大手外資がやっているようなところは酒販免許がそもそも取得できない場合が多いのでご注意ください。
レンタルオフィスも結構苦戦しますので、場所については慎重に検討してください。
行政書士の活用について
酒類販売業免許申請にあたっては行政書士の活用もご検討ください。
アロー行政書士事務所でも酒類販売業免許申請の代行・サポートをしています。
必要書類の作成・収集はもちろんですが、酒類販売業免許申請にあたってはそもそもどんな免許が必要なのか?というところから相談が必要となるケースが多くなっており、細かな商流から確認していく必要があります。
また、実際の申請にあたっては税務署との折衝も多くなりますので、手間の削減のためにも行政書士の利用をご検討ください。
アロー行政書士事務所では経歴書や取引承諾書等のひな形も用意しております。
ぜひご相談いただければと思います。