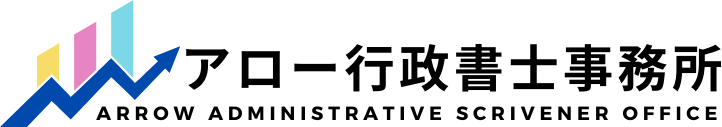「お酒を販売したいけど、酒類販売業免許っていろいろ種類があるみたい…。自分にはどの免許が必要なの?」「飲食店営業許可では未開栓のお酒は販売できないの?」
そんなご相談をよくいただきます。
実際、酒類販売業免許にはいくつかの種類があり、販売方法や取引相手によって必要となる免許が異なります。
店舗での販売なのかネット販売なのかなど販売方法によって必要な免許が異なる他、一般消費者に売るのか事業者に売るのかによっても変わってきます。
このページでは、酒類販売業免許の主な種類とそれぞれの特徴・対象となる販売形態についてわかりやすく解説します。
これから酒販免許の取得を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
なお、アロー行政書士事務所では、酒類販売業免許の取得をサポートしています。
ご不明な点や個別のケースでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
料金等を含めた酒類販売業免許申請代行サービス詳細はこちらからご確認いただけます。
お酒の販売に関する免許や許可にはどんなものがあるか?
お酒を販売するといってもそのスタイルは様々です。
居酒屋やレストランのようにお酒を開栓してコップに注いで販売提供するスタイルのお店もあれば、スーパーマーケットやコンビニのように未開栓の状態でお酒を販売をする形態などいろいろあるかと思います。
居酒屋やレストランなど、いわゆる飲食店を開業して開栓してお酒を提供したいというケースでは、飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届などの食品衛生法や風営法関係の許認可申請や届出が必要となってきます。
一方で、スーパーや酒屋などの店舗を構えて未開栓のお酒を販売するスタイルであれば、酒税法に基づく酒類販売業免許が必要です。
このページで解説するのは、後者の未開栓のお酒を販売するための免許、つまり酒類販売業免許について解説していくこととなります。
もし飲食店経営をお考えでこのページにたどり着いてしまった場合は内容が異なりますのでご注意ください。また、飲食店営業許可等では未開栓のお酒は販売できませんのでご注意ください。
※最近は飲食店やバーが酒類販売業免許を取得するケースも増えてはいますので、飲食店が未開栓のお酒を販売したいケースについては別途ページで解説しているのでそちらもご覧ください。
酒類販売業免許の種類
酒類販売業免許は大きく分けると「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに分けられます。
そして、酒類小売業免許は「一般酒類小売業免許」と「通信販売小売業免許」などに更に分けることができます。
酒類卸売業免許は「全酒類」「ビール」「洋酒」「輸出」「輸入」「自己商標酒類」などにわけることができます。
| 免許の種類の大枠 | 免許の種類詳細 |
|---|---|
| 酒類小売業免許 | 一般酒類小売業免許 |
| 通信販売酒類小売業免許 | |
| 特殊酒類小売業免許 | |
| 酒類卸売業免許 | 全酒類卸売業免許 |
| ビール卸売業免許 | |
| 洋酒卸売業免許 | |
| 輸出入酒類卸売業免許 ※輸出と輸入は別の免許です。 | |
| 店頭販売酒類卸売業免許 | |
| 自己商標卸売業免許 | |
| 協同組合員間酒類卸売業免許 | |
| 特殊酒類卸売業免許 |
それぞれの違いについて簡単に見ていきましょう。
酒類小売業免許とは?
酒類小売業免許は、一般消費者や飲食店向けにお酒を販売するのに必要となる免許です。
コンビニやスーパーでお酒を販売する、酒屋を開いて店舗で消費者向けに販売する、ネットで不特定多数の消費者にお酒を売る、飲食店向けに配達専門でお酒を小売するといった際に必要となる免許です。
小売業免許なので、卸売はできません。
なお、飲食店向けにお酒を販売する際に、実務においてお酒を卸すという表現をすることもあろうかと思いますが、酒税法において、これは卸売ではなく小売に該当しますのでご注意ください。
また、販売場ごとに免許が必要なことにも注意が必要です。
この酒類小売業免許は、「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の2つに分類できます。
一般酒類小売業免許について
一般酒類小売業免許は、酒類の販売場において、一般消費者や酒場・料理店等のお酒を取り扱う接客業者(飲食店等)、菓子等製造業等に対して、品目問わずすべての酒類を小売できる免許となります。
原則販売場が立地する都道府県のみ販売が可能です。
2都道府県以上にまたがる場合は通信販売小売業免許が追加で必要とされるケースが多くなっています(税務署や担当官による)。
なお、必ずしも店舗を持たなければならないわけではなく、飲食店等だけに向けてお酒を販売する場合は事務所のみで問題ないケースがあります。
飲食店向けにお酒を販売するケースにおいては、酒類卸売業免許が必要であると誤解しているケースもありますが、酒類小売業免許が必要となります。
・一般消費者や飲食店、菓子製造等業者等向けにお酒を販売する(お菓子だとお酒の入ったチョコやパン、ケーキ等)
・すべての種類のお酒が取り扱える
・1つの都道府県内のみ販売可能(1都道府県内のみであれば通信販売も可)
・無店舗型も可(飲食店等のみに小売する場合)
通信販売酒類小売業免許について
2都道府県以上でインターネットやカタログ送付の方法等によりお酒を販売する場合は通信販売酒類小売業免許が必要です。
近年需要が増えている免許区分と言えるでしょう。
一般酒類小売業免許と異なり、販売可能な品目に制限があり、国産酒は課税移出数量3,000kl未満のお酒のみとなります。品目ごとにすべてのお酒が3,000kl未満である必要があります。免許取得後に新たな仕入先を増やす際も証明書は必要です。地方特産品を原料としたお酒等に該当する場合は製造委託数量3,000kl未満であれば課税移出数量3,000kl以上の事業者の製造でも可となります。
一方で、輸入酒は品目問わず通信販売が可能です。
3,000klというとあまりイメージが湧かないかもしれませんが、ザックリ記載すると国内大手のお酒は取扱いができないということに注意が必要です。
・一般消費者等に通信販売でお酒を売る
・取り扱い可能なお酒に制限がある(輸入酒は制限がないが国産酒は課税移出数量3,000kl未満※つまり大手国産メーカーのお酒は難しい)
・2都道府県以上に小売する場合は通信販売によらない方法でも通販免許取得してほしいと税務署に言われることが多い
特殊酒類小売業免許
これは文字通り特殊な場合に必要となる小売業免許です。
手引きや国税のサイトには、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許をいう。と記載がありますが、自分の会社の役員・従業員にのみ継続して販売するケース等特殊な場合とお考えください。
これから酒販免許を取ろうという方のほとんどの人にはあまり関係がない免許であり、実務でもそれほど遭遇することはありません。
酒類卸売業免許とは?
酒類卸売業免許は、酒類販売業者や酒類製造業者に対し酒類を継続的に販売することができる免許です。
酒類小売業免許が一般消費者・飲食店向けの小売だったのに対し、酒類卸売業免許は業者に販売、つまり卸売する場合に必要となることに違いがあります。
酒類小売業免許と同様に、販売場ごとに免許が必要です。
酒類卸売業免許は区分が多いのですが、ここでは実際の実務で需要の高い「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「輸出入卸売業免許」「自己商標卸売業免許」について取扱います。
全酒類卸売業免許について
全酒類卸売業免許はすべての種類のお酒の卸売りが可能な免許です。
他の卸売業免許と大きく違うのは、一部の例外を除いて、日本酒・焼酎が卸売りできるという点にあるかと思います。逆に言えば、日本酒・焼酎(泡盛含)の卸売りがしたいのであれば、全酒類卸売業免許が必要となります。
ただし、取得のハードルは非常に高く、年1回の抽選式で付与枠はかなり少ないです。
また、年間の見込み卸売量が100KL以上という基準があります。
つまり、一定の販売力が見込め、知識等も求められることになります。
・すべてのお酒が卸売りできる免許
・日本酒、焼酎を卸売りするなら基本的に全酒卸が必要
・一定の販売力が必要であり、要件も高い
・年1回抽選があり、申請順位がその抽選で決定する
ビール卸売業免許について
国産ビールを卸売りするのに必要な免許です。
全酒類卸売業免許ほどではありませんが、要件は高く、年間の卸売量が50KL以上の基準がある他、年1回の抽選に応じての申請となります。ただ、全酒類とは異なり枠が多いのと、枠が余ることもありますので、その場合は都度の申請が可能となります。
国産ビールを卸売りするのに必要な免許なので、輸入ビールであれば輸入酒類卸売業免許が必要となります。
また、ビールではなく発泡酒は洋酒卸売業免許に入りますのでご注意ください。
・国産ビールを卸売りするための免許
・枠が決まっているが余ることもある
・発泡酒は洋酒卸売業に入るので注意
・販売力等の要件は一定度高い
洋酒卸売業免許について
ここでいう洋酒とは、主に、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒となります。国産か輸入品かは問いません。
これらを卸売りする場合に必要な免許となります。
申請時に品目を指定しますが、全指定も可能な場合がありますので、そのあたりはエリア・税務署によるところがあるかもしれません。
なお、輸入酒類卸売業免許とも関連してくる免許となるため、各免許で出来ることを把握し、どちらを取る方が良いかを検討する場面も多くあります。
・発泡酒は洋酒卸売業免許
・あくまで税法上の洋酒であり、その定義が果実酒・甘味果実酒・ウイスキー・ブランデー・発泡酒・その他醸造酒・スピリッツ・リキュールとなり、国産か輸入かは関係ありません。
輸出・輸入酒類卸売業免許について
税務署の手引きを見ると輸出入卸売業免許となっているので輸出も輸入もできる免許だと勘違いされるケースもあるのですが、輸出と輸入はそれぞれ別の免許です。
この輸出・輸入はあくまで自己(自社)が輸入・輸出する場合に限って与えられるものとなります。
また、自己が輸出・輸入するのであれば酒類の品目は問いません。
・輸出と輸入は別々の免許
・自己が輸出・輸入する場合に限って与えられる免許
・品目は不問
自己商標卸売業免許について
自己(自社等)が開発した銘柄のお酒に限って卸売できる免許です。
酒類の品目は不問なのが特徴と言えるでしょう。
日本酒や焼酎も自己商標であると認められれば卸売りが可能であるということです。
ただし、自己商標であると認めてもらうための書類づくりは大変な場合も多いため、一定の注意は必要です。
・自己が開発した商標・銘柄のお酒に限る
・品目は不問
・自己が開発したことを何らかの形で証明していく必要がある
店頭販売酒類卸売業免許
会員となった酒類販売業者が直接来店してお酒を持ち帰るスタイルの問屋のような形態です。
あくまで会員として登録した酒類販売事業者のみとなりますので、会員登録が必要です。また、配達等はできません。
この免許の特徴としては、ビール・日本酒も取り扱いができるというところにあるかと思います。
日本酒や焼酎を卸売りするには「全酒卸」が必要と記載しましたが、全酒は取得のハードルが高いため、ビジネスモデルと合致するなら店頭販売酒類卸売業免許という選択肢も無きにしも非ずではあるかと思います。
・会員登録が必要
・お店に来てもらい直接引き渡す必要がある
・日本酒(清酒)やビールの取扱いもできる(品目に制限はない)
協同組合員間酒類卸売業免許
自身が加入する協同組合の組合員に対してお酒を卸売することができる免許です。あくまで自分が加入する組合の中での話なので、他の組合に卸売りすることはできません。
特殊酒類卸売業免許
手引き等には酒類事業者の特別の必要に応ずるため、、、との記載がありますが、こちらも特殊なケースのみ当てはまるものとなり、基本的にほとんどの方には関係がないものとなります。
酒類小売業免許と酒類卸売業免許の違いまとめ
酒類小売業免許と酒類卸売業免許の違いをザックリまとめると、仕入先・販売先が異なるということです。
酒類小売業免許は一般消費者・飲食店などに向けたお酒の販売であるのに対し、酒類卸売業免許は酒類業者や酒類製造業者への販売時に必要であることがわかるかと思います。
※輸出・輸入に関しては一部税務署ごとで解釈に違いがでることがあります。
また、申請時の違いという点においては、仕入先・販売先の承諾書が必要となるかどうかというのが大きな違いの一つであると言えるでしょう。
いずれにせよ、お酒の販売をするにあたって、「どこから仕入れ」、「誰に対して」、「どのような方法で」、「何のお酒を売るのか」、これを整理し、どの免許が必要なのかを考えていくこととなります。
複数の酒販免許が必要な場面も多くなっています。
■酒類小売業免許の概要をまとめると以下のようになります。
| 免許名称 | 販売先・販売形態 | 取り扱えるお酒の種類 |
|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | ・酒屋(酒販店) ・スーパー ・コンビニ ・百貨店 ・道の駅等の販売所 ・居酒屋へ配達 ・レストランへ配達 ・菓子等製造業等に販売 | 原則としてすべての種類のお酒 |
| 通信販売酒類小売業免許 | ・インターネット販売 ・カタログ販売 ・チラシ販売 | ・輸入酒は全種類可 ・国産酒は課税移出数量3,000kl未満(地方特産品は製造3,000kl未満) |
| 特殊酒類小売業免許 | 上記に当てはまらないもの | 限定条件が必要に応じて付与されます |
■酒類卸売業免許の概要をまとめると以下のようになります。
| 免許名称 | 販売先・販売形態 | 取り扱えるお酒の種類 |
|---|---|---|
| 全酒類卸売業免許 | ・酒類販売業者 ・酒類卸売業者 ・酒類製造者 | 原則としてすべての種類のお酒 |
| ビール卸売業免許 | ・酒類販売業者 ・酒類卸売業者 ・酒類製造者 | ビール |
| 洋酒卸売業免許 | ・酒類販売業者 ・酒類卸売業者 ・酒類製造者 | 果実酒・甘味果実酒・ウイスキー・ブランデー・発泡酒・その他醸造酒・スピリッツ・リキュール・粉末酒及び雑酒 |
| 輸出入酒類卸売業免許 ※輸入酒類卸売業免許、輸出酒類卸売業免許と輸出と輸入はそれぞれ別の免許です | ・酒類販売業者 ・酒類卸売業者 ・酒類製造者 ・国外酒類業者、国外消費者 | 自己が輸出・輸入する酒類であれば原則すべて可 |
| 自己商標酒類卸売業免許 | ・酒類販売業者 ・酒類卸売業者 ・酒類製造者 | 当該免許に該当するのであれば原則すべての酒類が可 ※開発した銘柄の酒類 |
| 店頭販売酒類卸売業免許 | ・会員の酒販業者等 | 原則すべての酒類が可 |
| 協同組合員間酒類卸売業免許 | ・所属する組合の組合員同士 | 原則すべての酒類が可 |
| 特殊酒類卸売業免許 | ー | ー |
酒類販売業免許の種類を知り適切な免許を取得する
先ほど記載したように、自社に必要な免許区分をしっかりと把握し、必要な免許区分で申請していくようにしましょう。
よくある勘違いとしては、飲食店向けにお酒を販売するにあたって卸売業免許が必要であると勘違いしているケースがあります。
小売りなのか卸売りなのか整理し、何のお酒をどうやって販売するのかしっかりと整理しておきましょう。
なお、酒販免許の申請は要件が高く、また必要書類も膨大です。
そもそも要件を満たしているかどうかがわからないという方も多いので、当事務所も含め、行政書士の活用もご検討ください。
アロー行政書士事務所でも酒類販売業免許申請をサポートしています。
料金等を含めた酒類販売業免許申請代行サービス詳細はこちらからご確認いただけます。
酒類販売業免許の取得・申請をサポートしています
アロー行政書士事務所は東京都立川市に所在しておりますので、東京都多摩方面の申請や神奈川県、山梨県、長野県を中心に全国対応もしておりますので、気軽にご相談ください。
どの酒類販売業免許を取得すべきか?で悩むケースも非常に多いため、やりたいビジネス内容をお話いただき、どの免許を取得すべきか?というところからサポートさせていただきます。
酒販免許も地域性があり、税務署ごとに若干解釈が異なることがございますので、どの地域で開業予定なのかなどもお伺いさせていただき、しっかりと対応させていただきます。