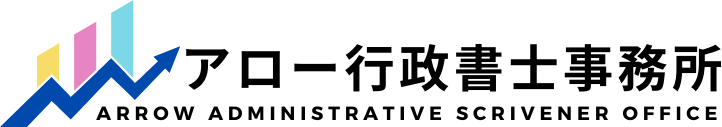酒類の製造業者へOEMでお酒の製造を委託し、独自のラベルのお酒の販売を検討するケースは近年増加しているように感じます。
地域の特産品を用いた地方創生に関連するものはもちろんのこと、芸能関係を含めたファンクラブ向けのオリジナルビール、アニメ・漫画等に関連したオリジナルのお酒の開発などさまざまなケースがあります。
ただ、独自のオリジナルラベルのお酒をつくって販売するといっても、誰に対してどんなお酒をどのように販売するのかによって必要な酒類販売業免許は変わってきます。
このページでは、OEMでオリジナルのお酒を造って販売する場合の酒販免許について見ていきたいと思います。
アロー行政書士事務所では酒類販売業免許の申請サポートサービスを提供しております。
酒類販売業免許申請でお困りであればぜひご相談ください。
酒類販売業免許の種類について知る必要がある
先ほど記載したように、誰に対して、どのようなお酒を、どのように販売するのかによって必要な免許は変わってきます。つまり、酒類販売業免許と一口にいってもさまざまな免許区分があり、どれか1つ、あるいは複数の免許が必要となるケースは意外と多くあります。そのため、自分がやろうとしているビジネスにおいてどの免許が必要になるかは初めに理解しておく必要があります。
酒類小売業免許と酒類卸売業免許の2つに大別できる
酒類販売業免許は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に分類できます。
酒類小売業免許は一般消費者や飲食店にお酒を販売(小売)する際に必要な免許となります。
酒類卸売業免許は酒販業者へお酒を販売(卸売)する際に必要な免許となります。
酒類小売業免許と酒類卸売業免許はそれぞれ細かく更に分類される
酒類小売業免許の中にも区分があり、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許があります。
一般酒類小売業免許は一般消費者に店舗を構えて販売したり、飲食店向けに配達の販売をするような際に必要となる免許です。通信販売酒類小売業免許は、一般消費者向けにネット販売等の通信販売の手段によりお酒の販売をする際に必要となる免許です。
酒類卸売業免許も細かく分類されており、洋酒卸売業免許や輸出入酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許などがあります。
このページでは詳細な説明は省きましたが、免許区分ごとで販売できるお酒の品目に制限があるなど、各免許ごとに出来ること、出来ないことがあります。
そのあたりも含めて詳細については以下のページよりご確認いただければと思います。
このページでは、各種免許についての違いをザックリと理解していただいた方向けにオリジナルのお酒を製造委託して販売するケースに絞ってみていきたいと思います。
自己商標酒類卸売業免許が必ずしも必要とは限らない
上記で酒類販売業免許の種類について説明しましたが、オリジナルのお酒を販売しようと検討されている方からのお問い合わせでよくあるのが、「自己商標酒類卸売業免許」の申請がしたいということでご相談いただくケースが多くなっています。
ただ、これは「酒類卸売業免許」なので、卸売をする際に必要となる免許ということになります。
なので、販売対象によっては必ずしも自己商標酒類卸売業免許が必要とは限らないということになります。
これを念頭に、パターン別にどのような免許が必要となるかを見ていきたいと思います。
オリジナルのお酒を一般消費者へ販売する場合は一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許が必要
酒造等へ製造委託してオリジナルのお酒を販売する場合において、販売対象が一般消費者であれば一般酒類小売業免許、あるいは通信販売酒類小売業免許が必要です。
自分の店で対面販売するなら一般酒類小売業免許
店舗を構えてお酒を陳列して販売するのであれば一般酒類小売業免許が必要です。
この免許は1都道府県内であればすべてのお酒が販売可能なので、オリジナルビールでもオリジナルワインでもオリジナル日本酒でもなんでも販売が可能です。
ただ、この免許ではネット販売はできませんので、ネット販売もするのであれば通信販売酒類小売業免許が別途必要です。
ネット販売するなら通信販売酒類小売業免許が必要
ネット通販等でオリジナルラベルのお酒を販売するのであれば、通信販売酒類小売業免許が必要です。
注意点としては、通信販売酒類小売業免許は、輸入酒であれば販売に特に制限はありませんが、国産のお酒の販売をする場合、課税移出数量3,000kl以上の製造者のお酒を販売することはできません。
したがって、大手の酒造には基本的にお願いできないということになります。
もっとも、OEMでオリジナルラベルのお酒を製造して販売しようと思う場合、地元の小さなワイナリー等である場合は多いでしょうからそれほど問題になるケースは多くない印象です。
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の両方を取得するケースは比較的多いかと思います。
居酒屋や飲食店へお酒を販売するなら一般酒類小売業免許
飲食店へお酒の販売をする場合に必要となる免許は小売業免許となります。したがってオリジナルのお酒を飲食店向けに小売するのであれば一般酒類小売業免許が必要ということになります。
飲食店への販売は卸売ではなく小売であることにご注意ください。
酒類販売業社などへ卸売をするなら自己商標酒類卸売業免許が必要
酒販業者向けにオリジナルのお酒を卸売をするのであれば自己商標酒類卸売業免許が必要となります。
この免許は販売できるお酒の品目に制限がないので、自社で開発したお酒であればすべて卸売が可能です。
通常、日本酒や焼酎、ビールを卸売しようと思った際は全酒類酒類卸売業免許やビール卸売業免許等の取得難易度が高い卸売業免許が必要となるので、そういった意味では広い品目が卸売可能な免許という大きなメリットがあります。
なお、あくまで自社(自己)が開発したお酒の卸売に限りますのでご注意ください。
オリジナルラベルのお酒の販売にあたって酒類小売業免許で問題ないケースも意外と多い
冒頭にも記載しましたが、OEMでオリジナルラベルのお酒を製造委託して販売しようと思った際に、自己商標酒類卸売業免許の申請がしたいということで検討される方は多いのですが、よくよく内容を整理すると一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の取得がむしろ必要であるというケースはあります。
そのため、改めての記載となりますが、「どのようなお酒を」「誰に対して」「どのような方法で販売するのか」を整理していただき、必要な免許を特定していくようにしましょう。
なお、実際に実務においては商流が複雑な場合も多くありますので、税務署と調整しながら進めていくことが重要です。
アロー行政書士事務所の活用もご検討ください
近年OEMによるオリジナルのお酒の製造・販売が増加しているようです。
品目としては日本酒やビール、ワインなどが多い傾向ですが、近年はウイスキーやジン、リキュールも増えているようです。
このページで記載したように、商流を明確にし、どのような免許が必要かを見極める必要がある他、酒類販売業免許申請にあたっては税務署との折衝から必要書類の作成まで含め大きな手間がかかります。
そのため、酒類販売業免許申請にあたってはぜひ行政書士の活用もご検討ください。
アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請の代行・サポートサービスを提供しております。
お困りであれば気軽にご相談ください。