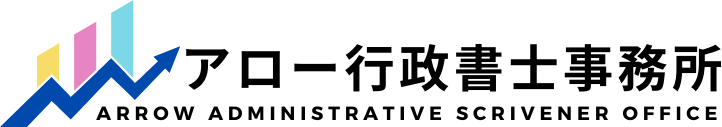酒類販売業免許申請にあたり、自分は要件のクリアができているのだろうか?と疑問に感じる方は意外と多くいらっしゃいます。
このページでは酒類販売業免許申請の要件の全体像について解説するとともに、注意が必要な内容についても記載していきます。酒類販売業免許取得を検討中の方はぜひご参考ください。
アロー行政書士事務所では要件のクリアができていそうかどうかという点の相談から申請の代行まで広く酒類販売業免許取得をサポートしています。
酒類販売業免許申請でお困りでしたらぜひご相談ください。
酒類販売業免許申請にはどんな要件がある?全体像を見る
酒類販売業免許取得の要件は大きく4つのジャンルに区分できると考えます。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件
需給調整要件などなかなか見慣れない言葉もあるかもしれませんが、1つずつ見ていきましょう。
1.人的要件について
人的要件は文字通り申請する人に関する要件となり、きちんと税金は納めているか?過去に犯罪歴等はないかといったものを確認するものとなります。
具体的には以下の要件となります。
※わかりやすくするため一部記載を省略・簡略化しています。
- 申請者が、酒類製造免許や酒類販売業免許、アルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがあり、その取消処分を受けた日から3年を経過していること。
※免許を取消された会社でその原因となった事実が発生する前の1年以内に役員だった方においてはその会社が免許を取り消された日から、3年が経過していること。 - 申請者が申請前2年内において、国税・地方税の滞納処分を受けたことがないこと。
- 申請者が国税・地方税に関する法令等に違反して、罰金刑や通告処分を受けたことがある場合には、それらの刑の執行を受けることがなくなった日等から3年を経過していること。
- 申請者が、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法・暴力行為等処罰に関する法律の規定により罰金刑に処せられた者である場合には、その執行等を受けることがなくなった日から3年を経過していること。
- 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。
ざっくり記載すると、過去に税金を滞納したり、何か犯罪をしてしまったりしているケースでは酒類販売業免許の取得ができない場合があるということです。
該当しないケースが大半ですが、稀に税金を滞納していたという方もいらっしゃるためご注意いただきたい事項でもあります。
また、過去にお酒やアルコールに関する許認可の取消を受けたことがある、あるいはそういった会社での役員経験がある場合もご注意ください。すぐの取得が難しい場合があります。
場所的要件
酒類販売業免許申請で意外と厳しいのが場所的要件です。手引きには以下のように記載されています。
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。
具体的には、
①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと。
②上記の場合には申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要となります。
(注) 例えば、狭あいな店舗内の一部を賃借等して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されているとは認められません。
参考:一般酒類小売業免許の手引きより
と記載されています。あっさりと記載されていますが、意外と場所的要件はやっかいです。
要するに、居酒屋等の飲食店では原則として酒類販売業免許が取得できないということになります。ただ、②に記載したように、明確に区分できていれば飲食店等でも免許は取得可能であり、実際に取得している飲食店等はあります。
また、自社ではなく、知り合いの会社のオフィスのデスクを1つ借りて酒類販売業免許を取得するといったことをすることも上記に照らして考えると難しいこととなり、もしそうするのであれば、明確に区分することが求められます。
この他、レンタルオフィスの利用の際にも注意が必要でしょう(なお、バーチャルオフィスを販売場とするのは不可です)。
ザックリ記載すると、しっかりと他の主体と区分されているということが1つ重要な要素だということになります。
賃貸借契約書の修正もしくは承諾書が必要な場合が多い
実際の申請にあたっては賃貸借契約書の提出が求められますが、契約書上での使用目的に酒類販売業で使用する記載がない場合、税務署は販売場として認めてくれないケースも多くあり、この場合は別途承諾書の提出が求められるケースが多くなっています。
この他、賃貸人と所有者が異なる場合でも所有者からの承諾書が求められるかと想定されます。
後は、自己所有の分譲マンションや賃貸のマンション等で酒類販売業免許を取得しようと思う際は、管理組合等からの承諾書、誓約書等が求められます。自宅マンション等での開業を目指すケースではこの承諾書を得るのが非常に難しく、断念せざるを得ないケースがあります。
土地の地目が農地(田や畑)は酒類販売業免許取得できないので注意
土地の地目が農地の場合は注意が必要です。
地方の方で実家を販売場として酒類販売業免許の申請をしようと思った際に土地の地目が農地だったということがあるためご注意ください。
広さに関する要件はないが区分されていることが重要
酒類販売業免許以外の許認可関連の場所的要件においては、広さが問題になるケースが一定度ありますが、酒類販売業免許においては特に広さに関する要件は定められていません。
なので、免許区分によっては机と椅子、プリンター、パソコンが入るぐらいの手狭なワンルームくらいの広さのオフィスで免許を取得されるケースもあります。
合理的に考えて、この広さで実務を行うのは不可能では?という形でなければ基本的に広さは問題ない場合が多くなっています。
ただ、自宅兼事務所といった形でマンションで酒類販売業免許を取得しようと思う際は生活するための場所と酒類販売業を行う場所とを明確に区分できるようにしてください。具体的には複数部屋ある1部屋を販売場にするといった形です。
経営基礎要件
手引きには以下のように記載されています。
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。
具体例として示されているのが、
- 国税・地方税を滞納している
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
- 直近の決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている
- 直近3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の 20%を超えるの欠損を生じている場合
- 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
- 申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
- 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
- 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
特に注意が必要なのが、3・4の決算に関する要件と8の経験値に関する要件です。
赤字が続いていたり繰越損失が大きい場合は注意が必要(3と4)
決算要件が満たせずに酒類販売業免許取得を断念するケースも一定度ございます。
3年連続大きな赤字を出している、繰越損失が大きくなっている場合は特に注意が必要です。
資本等の額とは、資本金に資本剰余金及び利益剰余金を足し、そこから繰越利益剰余金を引いた額を指しています。
資本等の額が繰越損失を上回っているかどうか(3について)
資本等とは、
①資本金+②資本剰余金+③利益剰余金-④繰越利益剰余金=資本等
ということになります。この額が繰越損失(繰越利益剰余金)より大きいのか小さいのかということになります。言い換えると、
・繰越利益剰余金がそもそもプラスである、
・繰越利益剰余金(繰越損失)がマイナスの場合、繰越損失額が資本等の額を超えていなければOKです。
たとえば、
①資本金100万円
②資本剰余金30万円
③利益剰余金▲100万円
④繰越利益剰余金▲100万円
の会社があったとします。
この会社の資本等は、①100万円+②30万円+③▲100万円-④▲100万円=130万円ということになります。
そして、④の繰越損失の額は100万円であり、資本等の額は130万円で繰越損失よりも資本等が大きいので、3の要件はクリアできているということになります。
逆に、利益剰余金が▲200万円、繰越利益剰余金も▲200万円であったならば、以下のようになり、3の要件がクリアできないということになります。
①100万円+30万円+▲200万円-▲200万円=資本等130万円
繰越損失200万円>資本等130万円
つまり、要件を満たせないということになり、酒類販売業免許の取得が難しいということがわかります。
このページではザックリとした決算書の記載になっているので、自社の決算書を見てよくわからないという場合は顧問税理士等にご確認頂いてもよいかと思います。
直近3事業年度で資本等の額の20%を超えるの赤字が出ている場合(4について)
3期連続で赤字が出ている場合にはこちらの要件にも注意が必要です。
赤字が続いている場合、直近3期分の損益計算書を確認いただき、先ほど計算した資本等の額の20%を超える赤字が続いていないか3期分すべてご確認ください。
①資本金100万円
②資本剰余金30万円
③利益剰余金▲100万円
④繰越利益剰余金▲100万円
先ほどのこちらの例で行くと、資本等の額は130万円ですので、26万円を超える赤字が出ていないかどうかをチェックしてください。
これはあくまでこの期の分の数値なので、3年分各事業年度これを計算してください。
3期連続で資本等の額の20%を超える赤字が続いている場合は酒類販売業免許の取得が難しい状況となります。
なお、あくまで3期連続なので、1期でも黒字があれば問題ありません。赤字が続いている場合にはご注意ください。
経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者であること(8について)
この経験に関する要件も意外と重要です。
大まかに記載すると、お酒の販売に関する業務経験・知識があるのか?経営経験・知識はあるのか?といったことが重要な要素となってきます。特に経営経験(能力)は重要です。
免許区分ごとで若干変わってくる部分もあるので、大まかな傾向を免許区分ごとに記載させていただきます。
なお、酒類販売業免許の種類を解説したページもありますので、免許区分がわからない方はこちらもご参考ください。
一般酒類小売業免許
手引きには、
経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者という記載があります。
酒類販売業あるいはそれに関連する事業における販売経験があるのかどうか、経営経験があるのかどうかということが問われています。
そして経験の目安の期間として3年というものが記載されています。
ただし、上記に記載した経験がなくても、
その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、
②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、
酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
との注意書きもあります。
つまり、お酒に関する商売の経験や経営経験はあった方がいいが、なくても総合的にさまざまな経験等を考慮して審査しますよという形になります。
実際に酒類販売業の経験がなく、経営者や取締役等の経験がない方でも、その他の経験等が評価されて免許が取得できるケースはあります。
具体的にこの経験があればOKというものでもないため、経験値を棚卸して検討していく必要があります。
通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許の手引きにも、経営経験や酒類販売業の経験に関する記載はありますが、「3年」といった期間の目安の記載はありません。
そのため、一般酒類小売業免許よりも経営経験等は厳しく見られない傾向にあると想定されます。実際に一般酒類小売業免許は厳しいが、通信販売酒類小売業免許なら免許が取得可能といったケースは結構あるかと思います。
輸出・輸入酒類卸売業免許
酒類業界での販売経験等は手引き上では求められていない他、手引きにも詳しくは記載されていないのですが、傾向から、輸出あるいは輸入の経験の有無、経営に関する知識・経験の有無、お酒の販売に関する経験の有無は総合的に見ているように感じます。
どちらかというと貿易実務の経験・知識の方が重要視されているように感じます。
洋酒卸売業免許・自己商標卸売業免許
一般酒類小売業免許と似たような要件となっています。
経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者という記載があり、例として、
・酒類販売業等に関連する業務・経営経験3年以上、
・又は酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者、
といった記載があります。
これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
と記載されています。
※酒類卸売業免許の手引きより
つまり、さまざまな経験を考慮するということになります。
あくまで肌感覚ですが、酒類小売業免許よりも酒類卸売業免許の方がお酒の販売や経営経験に対してシビアな印象を受けます。
地域や税務署ごとで判断が異なる場合が多い
どの程度の経験があれば免許が取得できるのかということに関しては、地域ごとでも異なるように感じます。
お酒の販売経験がなくても酒類販売管理研修の受講で知識麺はクリアできる地域もあればそうでない地域もあります。
また、担当官によっても言うことは結構変わってきます。
そのため、経験値が微妙な場合は慎重な対応が求められます。
酒類販売をするために必要な資金・設備等を有していること(9について)
これも意外と重要です。
酒類販売業免許には具体的に資本金・自己資金〇〇円以上といった要件が定められているわけではありませんが、仕入れや酒類の管理・販売が適切にできるのか?という観点から資金については審査されます。
申請書の販売計画上の仕入れ数が多い(100万円分くらい初月に仕入れをしている)のに資金が10万円しかなかったらNGとなってしまうのは言うまでもなくわかるかと思います。
ただ、お金がないと絶対に酒類販売業免許が取得できないかというとそうでもありません。
仮に計画上1,000万円の資金が必要だったと仮定して、事業資金が500万円しかなかったとしても、酒類販売業免許の取得ができれば1,000万円の融資が受けられることが確定している(証明は必要)という状況であれば、それは資金がある(予定)として認めてもらえます。
免許付与までに資金や設備が整うことが求められており、現時点で準備ができていないのであれば、整う証明をする必要があるということになります。
需給調整要件とその他
あまり聞きなれない言葉かと思いますが、手引きには以下のように記載されています。
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
申請者が、①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体、②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと が必要です。https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/01.pdf
販売先を構成員に限定する事業者や居酒屋等の飲食店では原則酒類販売業免許の取得ができないということが書かれています。
※飲食店に関しては原則不可であり、本ページでも記載したとおり、条件を満たせば取得は可能です。以下参考です。
どこから仕入れてどこへ販売するのかがある程度明確化している必要がある
需給調整要件とは異なる概念ですが、申請にあたっては、適切な仕入先、適切な販売先が少なくとも1つは定まっている必要があります。
免許を取ってから仕入先を探すといったことはできないためご注意ください。
どのような販売方法なのかやどの酒販免許を取得するのかで変わってくる部分もある
このページではあくまで手引きに基づいて一般的な内容を解説してきました。
ただ、実際の申請にあたってはお客様ごとで状況が異なりますし、事業形態も異なります。
要件自体が変わるということはありませんが、ご状況によって、必要な書類が変わって来たり、追加の要件等が発生するケースもあります。代表例としては飲食店が酒類販売業免許を取得する場合はいろいろ細かな資料の作成も必要となってきます。
ご自身のビジネス内容を整理し、要件が満たせそうかどうかまずは判断していくと良いでしょう。
なお、必要書類については以下のページをご参考ください。
行政書士の活用も検討
費用は少し多くかかってしまいますが、要件の確認から書類の作成・収集をご自身で行うのは手間がかかりますので行政書士を活用するのも一つの手段です。
アロー行政書士事務所ではお客様が酒類販売業免許の取得可能性がありそうかどうかなどを含めて、免許取得の可否から税務署との事前相談、申請書の作成、提出までしっかりとサポートしています。
提出書類の中にはECサイトサンプルの提出等も求められ、意外と手間がかかるものも多いので、もし自分でやるのが面倒だなと感じるケースでは行政書士の活用もご検討ください。
酒類販売業免許申請サポート・代行サービスページも合わせてご覧いただければと思います。