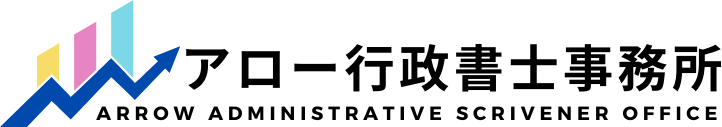このページでは、自己商標酒類卸売業免許とは何なのか?要件は?商標登録は必要なのか?など、自己商標卸売業免許申請にあたって疑問に思うポイントを中心に解説しています。
なお、アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請の代行・サポートを行っております。酒販免許申請でお困りでしたらぜひご利用をご検討ください。
自己商標酒類卸売業免許とは?どのようなケースで必要になるのか?
自己商標酒類卸売業免許とは、自社(自己)が開発した商標や銘柄のお酒を卸売することができる酒販免許です。
大まかに記載すると、自社が開発した銘柄のお酒を酒造等に委託製造(OEM)し、卸売することができる免許です。
地元の特産品を使ったオリジナルブランドのお酒を開発して卸売をしたいといったようなケースやオリジナルラベルのワインの卸売がしたい、アイドル・歌手の楽曲にちなんだオリジナル銘柄のお酒の卸売といったケースが一例として考えられます。
地域振興や芸能・メディア関係の方が取得したいという場合なども多いため、酒類卸売業免許の中では比較的相談が多い免許の1つだと思います。
なお、あくまで自社(自己)が開発したオリジナルのお酒である必要があり、他社が企画開発したものは対象となりません。
すべての酒類が取り扱える
自己商標酒類卸売業免許の特徴は品目を問わず、すべての酒類が対象だという点があるでしょう。
日本酒やビール、焼酎を卸売する場合、通常であれば全酒類卸売業免許やビール卸売業免許が必要となりますが、これらの免許がなくても卸売が可能となります。
全酒卸もビール卸も免許取得要件は非常に高いのですが、自己商標ということであれば自己商標酒類卸売業免許でこれらの免許が必要なお酒も卸売ができるということです。
なお、初めからすべて取り扱い可能なものとして免許がでるので品目を追加するための条件緩和の必要はありません。
一般消費者や飲食店へ小売するなら酒類小売業免許が必要
自己商標酒類卸売業免許はあくまで卸売をするための免許なので、小売をするなら一般酒類小売業免許等の小売業免許が必要です。
オリジナルのお酒を一般消費者へ販売したいというケースも多くなっておりますが、その場合は酒類小売業免許が必要なことにご注意ください。
なお、一般消費者や飲食店にしか販売しないのであれば自己商標酒類卸売業免許は不要で、該当する酒類小売業免許の取得のみで大丈夫です。卸売も小売もするのであれば、両方の免許が必要です。
商標登録をしている必要はない
自己商標酒類卸売業免許という名称から商標登録をしていないと免許申請ができないと思っている方もいらっしゃるのですが、登録していなくても大丈夫です。
ここでいう商標とはいわゆる商標登録のことを指しているわけではなく、オリジナルのラベル、独自ブランドといった形で自己が開発した銘柄といった形となります。
なので、商標登録が必須ということではありません。ただし、商標登録しているに越したことはありません。
自己商標であることを証明する必要はある
商標登録は不用ですが、自己が企画開発したお酒であることを証する書類等の提出は当然必要です。
企画書や製造元との契約書など、自己商標であることがわかる資料をいくつか用意し、わかるようにする必要があることにご注意ください。
免許取得後に申請時とは違った新たな企画のお酒の販売もできるのか?
全酒類のお酒の取扱いが可能であり、品目の追加にあたって条件緩和の申出は必要ないことを記載させていただいたところからもわかるかもしれませんが、免許取得後に免許申請時とは違うオリジナルのお酒を新たに卸売することは可能です。
オリジナルワインの卸売を行っていたが、その後、オリジナルビール、オリジナル日本酒といった形の展開も可能です。
なお、自己商標であることを証明するための書類(企画書や契約書等)はしっかり準備し保管するようにしてください。
共同で開発したオリジナルのお酒は自己商標に該当するのか?
あくまで自社(自己)が開発した場合が対象となる免許だとここまでで説明してきましたが、複数の事業者で共同で開発するケースもあろうかと思います。
基本的に当該企画の中心メンバーとして開発に携わっていることが客観的な資料から証明できるようであれば自己商標として認められるものと想定されます。
ただ、微妙なケースもあろうかと思いますので、税務署等への確認も入れながら進めるようにするといいでしょう。
自己商標酒類卸売業免許の要件は?
基本的に他の免許とそれほど要件は変わりありません。
大まかに記載すると、税金を滞納したことがないか?過去に大きな犯罪等をしたことがないか?といった人的要件のクリアと免許を取得する場所が適切であること、会社の経営状態が健全であること、お酒の販売に関する知識がしっかりあることといった内容となります。
会社の経営状態については、直近の決算において繰越損失の額が資本等の額を上回っていないこと、直近3期において資本等の額の20%を超える赤字を3期連続でだしていないことなどが必要です。
大きな損失を出しているケースや3期連続でそれなりに赤字が出ている場合は要注意です。意外と決算要件を満たせないケースがあるためご注意ください。
また、営業所の所在地の地目が農地ではないか、酒類販売業をすることが契約書上でわかるかなどもご確認ください。
その他酒類業界での経験の有無(あるいはそれにかわる何か)などを確認させていただく形となります。
自己が開発したオリジナルのお酒を証明する書類
途中でも記載しましたが、商標登録の必要はありませんが、自社が開発したものであることを証明するための資料は必要です。
契約書や企画書などがそれに該当します。
客観的にわかるようにする必要があります。
自己商標酒類卸売業免許申請でお困りなら
自己商標酒類卸売業免許を始めとして、酒類販売業免許は意外と複雑で面倒な手続きです。
税務署との調整も必要となり手間がかかることからなかなか自分で進められないという方も多くいらっしゃいます。
もし申請等でお困りでしたらアロー行政書士事務所の活用もご検討いただけましたらと思います。